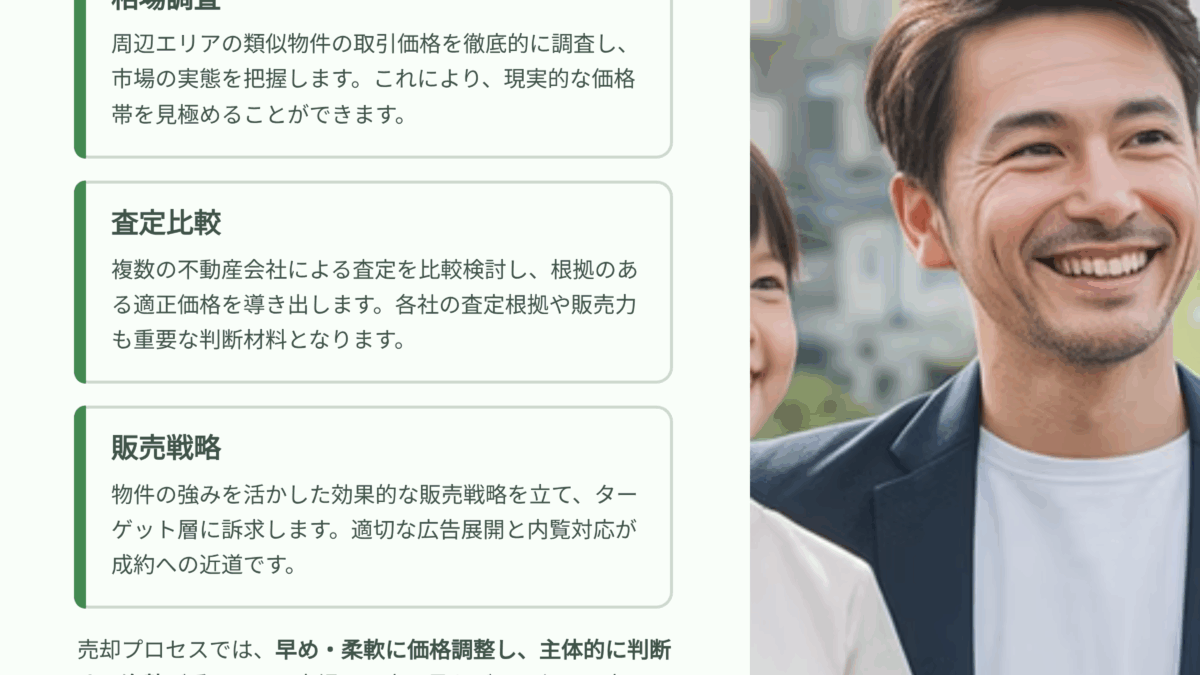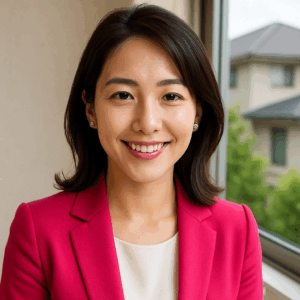
不動産売却で一番失敗しやすいのが「価格設定」です。高すぎても安すぎても後悔しますよね。売れ残りを防ぐ適正価格の考え方を整理しました。目次を見て必要なところから読んでみてください。
価格設定で失敗するとどうなる?売れ残りリスクの実態
「せっかく不動産を売り出したのに、なかなか売れない…」
「最初に強気の価格で出したのが裏目に出たのでは?」
「下げるべきか、このまま待つべきか、どう判断したらいいの?」
不動産売却でよくある悩みのひとつが、価格設定の失敗による売れ残りです。価格は一度つけたら変更できないものではありませんが、最初の印象が悪いと買い手の心理に大きく影響します。売れ残りが長期化すれば、「売れない物件」というレッテルが貼られ、結局さらに値下げせざるを得ないことも少なくありません。
では、価格設定を誤ると具体的にどんなリスクがあるのでしょうか?そして、どんな価格の付け方が売れ残りを招きやすいのでしょうか。
売れ残り物件が抱えるデメリット
売れ残りの一番の問題は、売却価格の下落リスクです。
不動産ポータルサイトでは、新着物件ほど注目されやすく、最初の数週間が勝負といわれています。そのタイミングを逃すと、閲覧数は激減します。
例えば、築20年の戸建てを3,800万円で売り出したケース。相場は3,500万円前後だったにもかかわらず、売主が「できれば少しでも高く」と強気に設定した結果、3か月経っても内覧希望がほぼゼロ。最終的に3,200万円まで値下げしてようやく成約しました。結果的に相場以下での売却になってしまったのです。
また、売れ残り期間が長くなると「何か欠陥があるのでは?」と疑念を持たれます。たとえ建物に問題がなくても、買主は心理的に避けがちになります。これは「レッテル効果」と呼ばれ、売主にとっては不利にしか働きません。
さらに、ローンが残っている場合は毎月の返済負担が続き、固定資産税や管理費などの維持費もかかり続けます。売れ残りは、金銭的・心理的な負担を大きくする要因になるのです。
売れ残りやすい価格設定の典型例
では、どんな価格設定が失敗を招きやすいのでしょうか。典型的なパターンを見ていきましょう。
- 相場より高すぎる価格
最も多い失敗です。特に一括査定サイトで出てきた「一番高い査定額」を鵜呑みにして設定すると、相場から乖離してしまうことが少なくありません。不動産会社は「専任契約を取るために高めに出す」こともあるので注意が必要です。 - 「値下げ前提」の上乗せ価格
「とりあえず高めに出して、反応がなければ下げればいい」と考える売主もいます。しかし市場はシビアで、最初の印象が悪ければ二度と注目されないことも多いです。結局は「売れ残り物件」と見られ、最初から相場に近い価格で出した方が結果的に高く売れるケースが多いのです。 - 近隣事例を無視した独断的な価格
「うちの家はリフォームしたから」「思い入れがあるから」といった感情で価格を決めるパターンも危険です。買主は感情ではなく、市場価格を基準に判断します。感情的な価格は、買主にとっては「割高」としか映りません。 - 不動産会社に丸投げしてしまうケース
担当者の提案をそのまま受け入れるのもリスクがあります。会社によっては「早く売りたいから低めに設定する」こともあるからです。適正かどうかを判断するには、複数社の査定を比較することが必須です。
まとめると、不動産売却で売れ残りを防ぐには「最初の価格設定」が非常に重要です。強気すぎても失敗し、感情に流されても失敗する。データに基づいた適正価格をどう見極めるかが成功の分かれ道になります。
次回は、適正価格を決めるために知っておくべき基礎について、具体的な調べ方や査定方法を詳しく解説していきます。
関連記事:家の査定額を正しく見極める方法を知りたい方はこちら
🔥 今だけ!三井のリハウス無料査定キャンペーン
39年連続No.1の実績で、あなたの家も2人に1人が提案価格以上で成約
⏰ 入力60秒・完全無料・しつこい営業なし
今すぐ無料査定を申し込む → ※ 査定したからといって売却する必要はありません不動産売却で一番大きなカギを握るのが「適正価格の設定」です。
「高すぎれば売れ残る、安すぎれば損をする」——この難しいバランスをどう見極めるかが、成功と失敗を分けます。
あなたは自分の家や土地の“相場価格”を把握していますか?
査定を受けるときに「机上査定」と「訪問査定」の違いを理解していますか?
そして、複数社の査定を比較した経験はありますか?
これらを知らないまま売却に進むと、気づかないうちに数百万円単位で損をしてしまう可能性があります。ここでは、適正価格を決めるための基礎を整理していきましょう。
不動産相場の調べ方と活用方法
不動産の相場を調べるには、いくつかの方法があります。代表的なのは以下の3つです。
- 不動産ポータルサイトでの検索
SUUMOやアットホームなどのサイトで、同じエリア・築年数・間取りの売出価格を調べる方法です。ただし「売出価格=実際に売れる価格」ではありません。売れ残り物件も混ざっているため、相場より高めに表示されているケースも多いのです。 - 国土交通省の「不動産取引価格情報検索」
実際に成約した価格を調べられる公的データベースです。エリアや築年数を入力すれば、実際に「いくらで取引されたのか」がわかります。信頼性が高く、相場の基準にしやすい情報です。 - レインズ(不動産流通標準情報システム)
本来は不動産会社しか見られませんが、ここには最新の取引事例が集まっています。売主自身は直接アクセスできないものの、不動産会社に依頼すれば「周辺での成約事例」として情報提供してもらえることがあります。
これらを組み合わせて調べると、「このエリアではいくらで売れているのか」という実態を把握できます。相場を知らないまま不動産会社に依頼すると、提示された査定額が高すぎても低すぎても気づけないので、必ず事前に調べて基準を持っておくことが大切です。
机上査定と訪問査定の違いと注意点
不動産会社に査定を依頼するときは、「机上査定」と「訪問査定」という2種類の方法があります。
- 机上査定
住所・築年数・間取りなどのデータをもとに、類似物件の成約事例や市場動向を参考に算出する方法です。手軽でスピーディーですが、あくまで概算。売出価格の目安としては使えますが、精度は高くありません。 - 訪問査定
不動産会社の担当者が現地を訪れ、建物の状態や日当たり、周辺環境、リフォーム履歴なども含めて評価する方法です。机上査定より具体的で、実際の売却価格に近い額を算出できます。
注意点としては、机上査定だけで価格を決めないことです。数字だけを見ると「思ったより高く売れる!」と期待してしまいますが、実際に売れるとは限りません。特に一括査定サイト経由の机上査定は、他社より高く出して契約を取ろうとする傾向があるため、過信は禁物です。
本気で売却を考えるなら、必ず訪問査定を受け、現地を見てもらったうえで価格を検討するようにしましょう。
複数社査定を比較する重要性
査定は不動産会社によって大きく差が出ることがあります。同じ物件でも、ある会社は「3,200万円」、別の会社は「2,800万円」といった具合に、数百万円単位で違うのは珍しくありません。
なぜこんなに差が出るのか?
理由は、不動産会社によってデータの分析方法や得意分野、販売戦略が異なるからです。
例えば、大手不動産会社は全国的なデータを活用して「市場全体から見た価格」を重視する傾向があります。一方、地域密着型の不動産会社は、地元の購入者層や細かな事情を把握しており「このエリアならこの価格で決まる」といったリアルな感覚を持っています。
だからこそ、複数社の査定額と提案を比較することが必須なのです。単に金額だけを見るのではなく、以下の点もあわせて確認しましょう。
- 提案される販売戦略は具体的か
- 売却までの期間をどのように見積もっているか
- 値下げの可能性についても説明しているか
複数の視点を持つことで「相場から乖離していないか」を冷静に判断できます。そして最終的に「納得して依頼できる会社」を選ぶことが、適正価格での売却につながります。
適正価格は、一度決めたら変えられない“固定された数字”ではありません。相場の調査、査定方法の違い、複数社の比較。これらを踏まえて柔軟に見極めることで、売れ残りリスクを避けながら納得のいく売却を実現できるのです。
関連記事:不動産査定の基準と相場感を理解できる解説
本格的に売却を考えている方は、信頼できる大手不動産会社での査定から始めてみてください。
三井のリハウスで適正価格を無料査定してみる
売れ残りを防ぐための価格戦略
不動産売却において、最も悩ましいのが「価格戦略」です。
最初の売り出し価格をどうするか? 値下げはいつ、どのくらい行うべきか?
そして、販売活動とのバランスはどう取ればよいのか?
これらを誤ると、せっかくの物件が“売れ残り物件”として扱われ、結局相場より安く手放さざるを得なくなることがあります。では、どのように戦略を立てれば売れ残りを避けられるのでしょうか。
最初の売り出し価格をどう設定するか
売却の成功は「最初の価格設定」で8割決まる、と言われるほど重要です。
買主は、ポータルサイトに新着物件が掲載されたときに最も注目します。ここで「割高だな」と思われると、リストから外され、二度と見てもらえないことも多いのです。
具体的には、相場価格の±5%以内での設定が理想です。
例えば相場が3,000万円なら、2,850〜3,150万円程度の範囲に収めるのが無難です。強気に設定するなら上限ギリギリに、早く売りたいなら下限寄りに設定するのがポイントです。
よくある失敗は「相場より1割以上高く出す」ケース。最初に強気で出しても、結局は値下げを繰り返して相場より安く売れることが多く、結果的に損をしてしまいます。
つまり、最初の売り出し価格は「早期売却」と「利益確保」のバランスを意識しながら、慎重に決めることが重要です。
値下げのタイミングと考え方
不動産は、売り出しから3か月以内が勝負とされています。この期間に反応が薄い場合は、価格を見直すサインです。
ただし、値下げは闇雲に行えば良いわけではありません。ポイントは以下の通りです。
- 最初の1か月間で内覧がほとんどない場合
設定価格が高すぎる可能性が大きいため、早めの見直しが有効です。 - 2〜3か月経っても購入申し込みがない場合
相場とズレている証拠です。5%程度の値下げを検討しましょう。 - 長期化するほど効果が薄れる
半年以上経ってからの値下げは「売れ残り物件」と見られるため、買主の印象を回復しづらくなります。
つまり、値下げは「早め・小刻みに」が鉄則です。大幅な値下げを後からするよりも、タイミングよく調整した方が売主の利益を守れます。
販売活動と価格の関係性
価格戦略は、販売活動とセットで考える必要があります。いくら適正価格を設定しても、広告や内覧対応が弱ければ売却は難しいからです。
例えば、同じ3,000万円の物件でも、写真が暗かったり、物件情報が簡素だったりすると、買主は「他にもっと良い物件がある」と判断してしまいます。逆に、プロの撮影や丁寧なキャッチコピーがあるだけで反響が倍増することもあります。
さらに、販売活動の強弱は不動産会社の方針によっても差が出ます。大手は広域的な集客に強く、地域密着型は近隣需要の把握に強い。どちらを選ぶかで、同じ価格でも売れやすさは変わってきます。
つまり、価格と販売活動は車の両輪。価格を適正にしても販売が弱ければ売れ残るし、販売を強化しても価格が高すぎればやはり売れ残ります。両者のバランスを取ることが、売却成功への最短ルートなのです。
適正価格の設定は「相場」「値下げタイミング」「販売活動」の3点を組み合わせて考える必要があります。売れ残りを防ぐには、相場を基準にしつつ柔軟に調整し、販売活動を最大限に生かす戦略が不可欠です。
関連記事:岡山市の不動産売却おすすめ業者ランキング
適正価格と販売戦略を同時にサポートしてほしい方は、大手不動産会社に相談するのも効果的です。
三井のリハウスで無料査定を依頼する
状況別に考える適正価格の付け方
不動産の価格設定は、物件の特性や売却の事情によって大きく変わります。
「人気が集中する物件」と「売れにくい物件」では戦略がまったく違いますし、相続や住み替えといったケースでも注意すべきポイントがあります。
あなたの物件は「需要が高いタイプ」でしょうか?それとも「売却に時間がかかりやすいタイプ」でしょうか?
また、売却の事情は「できるだけ早く売りたい」のか、「少しでも高く売りたい」のか?
ここでは、状況別に適正価格の考え方を整理していきます。
人気物件と売れにくい物件の価格戦略の違い
まずは「物件の需要」によって戦略を分ける必要があります。
人気物件の特徴
- 駅近(徒歩10分以内)
- 築浅(10年以内)
- 大規模マンションの中層階・角部屋
- 学区や生活環境が良好
こうした物件は、買主からの問い合わせが集中しやすいため、やや強気の価格設定でも成約につながることが多いです。相場の上限近く、もしくは+3〜5%を目安にスタートしても検討余地があります。
一方で、売れにくい物件は戦略を変える必要があります。例えば…
- 築30年以上の戸建て
- 駅から徒歩20分以上の立地
- 狭小地や変形地
- 管理状態の悪いマンション
こうした物件を人気物件と同じ価格戦略で出すと、売れ残る可能性が高いです。むしろ、相場の下限寄りで早期売却を狙う方が有利になる場合もあります。
つまり、「需要が強いか弱いか」を客観的に判断し、それに応じて価格戦略を調整することが不可欠です。
相続・空き家・住み替え時の価格設定の注意点
売却理由によっても価格設定の考え方は変わります。代表的なケースを見ていきましょう。
1. 相続物件の場合
相続で取得した家は、売主にとって「早く処分したい」ケースが多いです。固定資産税や管理の負担があるため、長期化は避けたいところ。相場の上限を狙うよりも、適正価格で確実に売り切ることが重視されます。場合によっては解体して更地にする方が早く売れることもあります。
2. 空き家の場合
空き家は維持管理が難しく、時間が経つほど劣化して価値が下がります。また、防犯や近隣への迷惑といったリスクも。売却を急ぐ必要があるため、相場の下限での設定+短期決戦を意識した方が良いです。自治体によっては「特定空き家」として指定されると税負担が増えるため、放置は禁物です。
3. 住み替えの場合
住み替えでは「売却益」と「購入資金」のバランスが重要になります。高く売りたい気持ちはあるものの、次の購入スケジュールがあるため、売却が長引くと資金繰りに影響します。この場合は、相場の中心〜やや下限でスムーズに売る戦略が現実的です。特にダブルローンを避けたい人は、価格を強気にせず早期売却を優先すべきです。
まとめると、適正価格の付け方は「物件の需要」と「売却理由」の二つを軸に考えるのがポイントです。需要が高ければ強気戦略も可能ですが、相続や空き家のように維持負担が大きい場合は、相場を意識した柔軟な価格設定が必要になります。
関連記事:不動産売却で後悔しないための必読ガイド
売却事情に合わせた最適な価格戦略を知りたい方は、プロの査定を受けてシミュレーションしてみてください。
三井のリハウスで無料査定を試してみる
よくある質問と失敗回避のポイント
不動産売却では、多くの方が「なるべく高く売りたい」と同時に「できるだけ早く売りたい」と考えます。しかし現実には、その二つをどう両立させるかで悩む場面が多いです。さらに、「価格を下げずに売る工夫はあるのか?」「不動産会社に任せきりで大丈夫なのか?」といった不安も出てきますよね。
ここでは、よくある疑問に答えつつ、失敗を避けるための考え方を整理します。
「高く売りたい」と「早く売りたい」は両立できる?
結論からいうと、完全な両立は難しいが、工夫次第で近づけることは可能です。
一般的に「高く売る」ためには時間をかけて買主を探す必要があります。一方、「早く売る」ためには価格を相場の下限に近づける必要があります。この二つは相反する条件なので、バランスを取ることが大切です。
例えば、相場が3,000万円の物件なら、3,150万円で売り出して内覧の反応を見つつ、1〜2か月で動きがなければ早めに3,000万円へ調整する。こうした柔軟な戦略をとれば、「高値狙い」と「早期売却」の両方に近づけます。
価格を下げずに売る工夫はある?
価格を下げずに売却したいなら、**「物件の魅力を高める工夫」**が欠かせません。
代表的な方法は以下の通りです。
- ホームステージング
家具や照明を工夫してモデルルームのように見せることで、第一印象をアップさせる。 - 小規模リフォーム・クリーニング
クロスやフローリングの張り替え、ハウスクリーニングで清潔感を出す。 - 高品質な写真と動画
暗い写真や雑然とした室内よりも、プロ撮影の写真や内覧動画の方が反響を得やすい。 - 販売活動の強化
複数のポータルサイト掲載やSNS広告など、露出を最大化する。
これらの工夫は数十万円の投資で数百万円高く売れる可能性を生むこともあり、「価格を下げずに売る」現実的な方法といえます。
不動産会社に価格交渉を任せても大丈夫?
不動産会社に価格交渉を任せるのは基本ですが、任せきりにするのは危険です。
営業担当者は早期成約を優先する傾向があり、「少し値引きすればすぐ決まります」と提案されることもあります。しかし売主からすれば、数十万円〜数百万円の違いは大きいもの。
信頼できる会社を選ぶことはもちろんですが、以下の点も意識すると安心です。
- 交渉方針を事前に共有しておく(最低ラインの価格を決める)
- 購入希望者からの条件提示を必ず確認してから判断する
- 複数の買主候補がいる場合は焦らず比較する
つまり、プロに任せる部分と自分で判断すべき部分を切り分け、**「主体的に関わる姿勢」**を持つことが、失敗を防ぐ最大のポイントになります。
不動産売却は、価格戦略と販売活動のかけ合わせで結果が決まります。焦って値下げするのではなく、工夫と交渉を重ねることで「納得の売却」に近づけるのです。
安心して売却を進めたい方は、大手不動産会社の経験豊富な担当者に相談するのも有効です。
三井のリハウスで無料査定を受けてみる