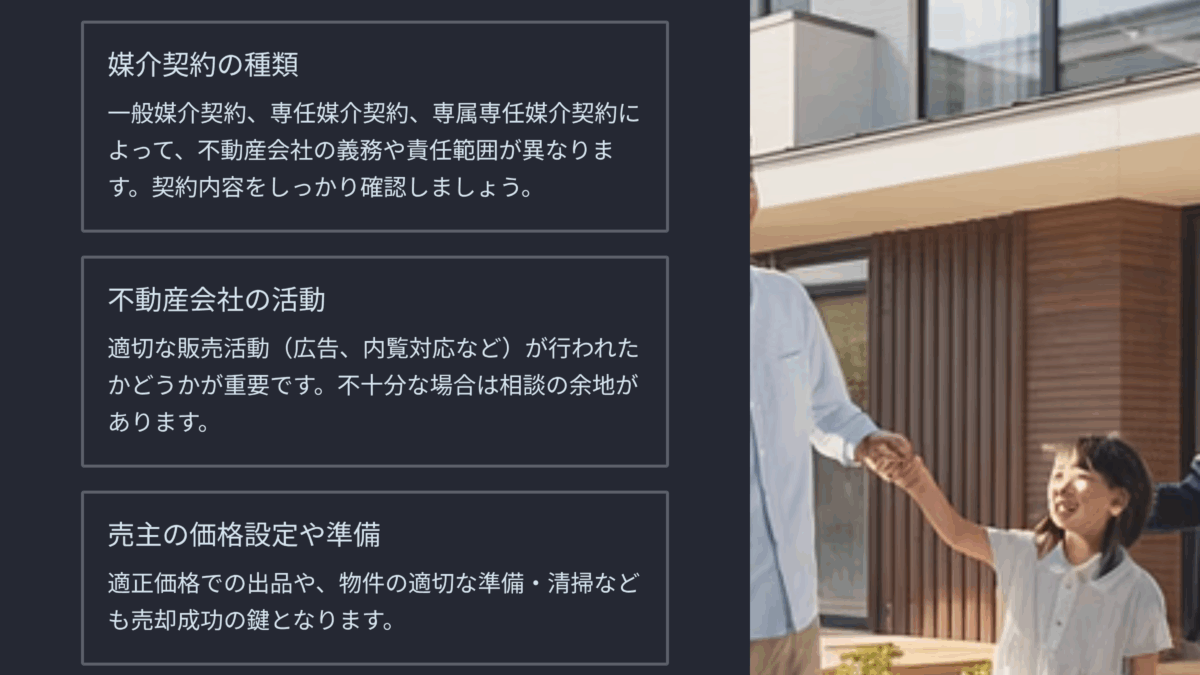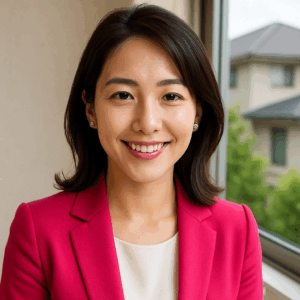
不動産売却で「売れなかったら誰の責任?」と不安に思う方へ。契約前の確認ポイントや費用、トラブル回避の工夫を解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
不動産売却は売れなかったとき誰の責任か
「せっかく不動産を売却に出したのに売れなかったら、誰が責任を負うのだろう?」
「仲介をお願いした不動産会社に責任はあるの?」
「それとも、売主である自分に原因があるの?」
不動産売却は人生の大きな決断のひとつです。ですが、思った以上に売れずに時間だけが過ぎるケースも珍しくありません。そのとき、責任の所在があいまいなまま契約を結んでしまうと、トラブルの原因になりかねません。
この記事では、不動産売却が売れなかったときの責任が「誰にあるのか」を媒介契約ごとに整理し、不動産会社と売主がそれぞれどこまで責任を負うのかを解説します。さらに、契約前に確認しておくべきポイントを具体的にご紹介します。
媒介契約の種類ごとの違い
不動産会社と結ぶ「媒介契約」には大きく3種類あります。
- 一般媒介契約
複数の不動産会社と同時に契約でき、自由度が高い反面、不動産会社の販売責任は限定的です。売れなかった場合でも、特段の責任を問うことはできません。 - 専任媒介契約
1社だけと契約する方式。不動産会社はレインズ(不動産流通機構のデータベース)への登録や定期的な報告義務があります。売れなかった場合でも法的な責任を不動産会社に問うのは難しいですが、活動内容が不十分であれば契約更新をしない選択肢があります。 - 専属専任媒介契約
最も不動産会社との関わりが強い契約形態で、自己発見取引(自分で買主を見つけること)ができません。売主にとって制約は強いですが、その分、不動産会社は毎週の報告義務などがあり、販売活動に対する責任感が比較的強まります。
つまり、媒介契約の種類によって「売れなかったときに不動産会社がどこまで責任を持つのか」は大きく変わるのです。
不動産会社が負う責任と限界
では、不動産会社が売却できなかった場合、責任を取ってくれるのでしょうか?
結論から言うと、不動産会社には「売れること」を保証する責任はありません。査定価格もあくまで「見立て」であり、必ずその価格で売れるわけではないのです。
ただし、不動産会社には「誠実に販売活動を行う責任」があります。例えば、
- レインズに登録しない
- 報告を怠る
- 内覧の調整を疎かにする
こうした行為は不動産会社の義務違反と言えます。実際に、売主が「全く動いてくれない」と感じるケースもあり、その場合は契約更新をせずに他社に依頼するのが一般的です。
売主自身に残る責任とは
一方で、売主にも当然ながら責任が残ります。
- 価格設定が市場相場から大きく外れている
- 物件の状態が悪く、内覧時に印象が悪い
- 売却時期を急ぎすぎて柔軟な交渉ができない
こうした要因は売主側の判断や準備不足に起因することが多く、「売れない責任」を不動産会社にすべて押し付けることはできません。
また、契約成立後には「契約不適合責任」といって、引き渡した不動産に欠陥があった場合には売主が責任を負う可能性があります。たとえ不動産会社が仲介していても、物件の状態に関する最終的な責任は売主にあるのです。
不動産売却で「売れなかったときの責任は誰が?」と考えるとき、答えは一方的ではありません。
- 不動産会社には誠実な販売活動を行う責任がある
- しかし「売れること」自体は保証されない
- 売主にも価格設定や物件準備などの責任がある
このように整理すると納得感があるのではないでしょうか。
契約前には必ず媒介契約の違いを理解し、不動産会社の販売体制や報告体制を確認しておきましょう。そうすることで、「売れなかった」という結果に直面しても、冷静に次の一手を選びやすくなります。
あなたは今、不動産をどのような形で売却しようと考えていますか?
そして、そのときに「責任の所在」を理解したうえで契約を結べそうでしょうか?
ぜひ、今回の内容を参考にして、納得のいく不動産売却に向けて準備を進めてみてください。売れなかった場合にかかる費用や影響
「売却活動をしたけれど、結局売れなかった…」
そんなときに気になるのは、費用はかかるのか? という点ですよね。
仲介手数料はどうなるのか?広告費は請求されるのか?契約を解除したら違約金はあるのか?
実際のところ、不動産売却は「売れなければ基本的に大きな費用は発生しない」仕組みになっています。ただし契約内容によっては思わぬ出費につながるケースもあるので注意が必要です。ここでは、売れなかった場合に考えられる費用や影響を整理しておきます。
仲介手数料は発生するのか
不動産売却の仲介手数料は、売買契約が成立したときに初めて発生します。
つまり、売れなかった場合は仲介手数料を支払う必要はありません。これは大きな安心材料ですよね。
ただし例外があります。契約の途中で「売主の都合で契約をキャンセルした」場合には、手付金返還や違約金が発生するケースがあります。例えば、買主が見つかって売買契約を結んだ後に「やっぱり売るのをやめたい」となれば、違約金を支払わなければなりません。
売れないだけであれば仲介手数料はゼロですが、「売主都合の中止」と「単に売れなかった」の違いは押さえておきたいところです。
広告費・キャンセル費用の扱い
次に気になるのは広告費です。
一般的な仲介契約では、不動産会社が自社の費用で広告活動(ポータルサイトへの掲載、チラシ配布など)を行います。そのため、売れなかった場合に広告費を請求されることは基本的にありません。
ただし、契約時に特約で「実費精算」と定められているケースがあります。例えば、特別に高額な広告を依頼した場合や、売主の要望で独自の宣伝をした場合などは費用負担が生じる可能性があります。
また、売買契約を結んだ後にキャンセルした場合には「違約金」や「手付金の放棄」といった金銭的影響があります。金額は契約内容によって異なりますが、売買価格の5〜20%が相場になることもあります。大きな出費につながるため、契約前に「解約時の取り扱い」を確認しておくことが欠かせません。
契約解除の流れと注意点
売れないまま契約期間(通常は3か月)が終了すると、媒介契約は自動的に満了となります。その後は更新するか、別の不動産会社に依頼し直すかを選べます。
契約途中で解除したい場合には、不動産会社に「媒介契約の解除」を申し出ればOKです。基本的に違約金は発生しませんが、以下の点に注意しましょう。
- 広告費が特約で実費精算になっていないか
- 売主の都合で売買契約をキャンセルする場合は違約金が発生する可能性がある
- 契約解除は書面で行い、証拠を残しておくのが安心
不動産売却は「売れるかどうか」に加え、「売れなかった場合にどうなるか」を理解しておくことで、余計なトラブルを防げます。
不動産売却は大きなお金が動く取引です。売れなかったときにどの費用がかかるのかを把握しておくことで、安心して次の一歩を踏み出せますよね。
あなたが今、不動産売却を検討しているなら「仲介手数料」「広告費」「契約解除の条件」の3点を必ず確認してみてください。
ここを理解しているかどうかで、売却の成否だけでなく、納得度が大きく変わってくるはずです。契約前に確認すべき重要ポイント
不動産売却は人生でそう何度も経験するものではありません。だからこそ、契約前の確認不足が大きな後悔につながりやすいのです。あなたは「どの契約を選べば安心できるのか?」「契約書のどこに注意すべきなのか?」を事前にイメージできていますか?
ここでは、不動産売却をスムーズかつ安心して進めるために、契約前に必ず押さえておくべきポイントを整理します。
媒介契約ごとの特徴と選び方
不動産会社と結ぶ媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があります。それぞれの特徴を理解して選ぶことが第一歩です。
- 一般媒介契約
複数の不動産会社と契約可能。売主の自由度は高いですが、不動産会社の販売活動は消極的になりやすい傾向があります。自分でも積極的に動ける方に向いています。 - 専任媒介契約
1社だけと契約しますが、自己発見取引(自分で買主を見つけて契約)が可能。レインズへの登録義務や2週間に1回の報告義務があるため、販売活動の透明性が高く、バランスが取れた契約です。 - 専属専任媒介契約
自己発見取引ができず、不動産会社経由でしか売却できません。その代わり、1週間に1回の報告義務があり、販売活動は手厚くなりやすいです。売却経験が少ない人や、密なサポートを望む人に適しています。
あなたの性格や売却方針に合う契約を選ぶことが、売却成功の大前提になります。
レインズ登録・報告義務の有無
媒介契約を結ぶときに見落とされがちなのが「レインズ登録」と「報告義務」です。
- レインズ登録
不動産流通機構が運営するデータベースで、登録すれば全国の不動産会社が情報を共有できます。専任・専属専任では登録が義務化されていますが、一般媒介では任意。レインズ登録がないと市場に広がりにくいため、契約前に必ず確認しましょう。 - 報告義務
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告が義務付けられています。進捗が分からないまま時間だけが過ぎるのを防ぐためにも、報告の頻度や方法を確認することが大切です。
「情報が広がるかどうか」「販売状況を知れるかどうか」は、売主にとって安心度を大きく左右しますよね。
契約不適合責任や免責条項の確認
もうひとつ見落とせないのが、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)に関する条項です。
- 契約不適合責任とは?
引き渡した物件に欠陥や不具合があった場合、売主が責任を負う義務のことです。例えば雨漏りやシロアリ被害など、売却時に把握していなかった不具合が後から見つかった場合、補修費や損害賠償を求められることがあります。 - 免責条項の有無
個人の売主同士の取引では、この責任を免除する「免責特約」を設けることが一般的です。ただし、不動産会社を介した契約や新築物件では免責できない場合もあります。
契約前に「責任がどこまで残るのか」「免責の範囲はどうか」を確認しておかないと、後で大きな出費につながる恐れがあります。
不動産売却は「契約を結んでから」ではなく、「契約を結ぶ前」にどれだけ準備をするかで結果が決まります。
- どの媒介契約を選ぶか
- レインズや報告義務の確認
- 契約不適合責任や免責条項の理解
この3つをしっかり押さえてから契約に臨めば、売れなかった場合や引き渡し後のトラブルにも冷静に対応できるでしょう。
あなたは今、契約前にこの3点を確認できていますか?もしまだなら、次回の打ち合わせで必ず担当者に確認してみてください。それが後悔しない不動産売却への第一歩になります。売却を成功させるためにできる工夫
不動産売却は「運」だけで決まるものではありません。準備の仕方や不動産会社との向き合い方次第で、売れるか売れないか、そしてどんな条件で売れるかが変わってきます。では、具体的にどんな工夫ができるのでしょうか?
不動産会社とのコミュニケーション
売却成功の大きなカギは、担当者との信頼関係です。
「最近問い合わせはあるのか?」
「内覧の反応はどうだったのか?」
「広告はどんな媒体で出しているのか?」
こうした質問を遠慮せずに投げかけてみましょう。
担当者の回答が具体的であれば安心できますし、逆に抽象的な説明しか出てこない場合は、活動が十分でない可能性もあります。
また、内覧後のフィードバックは非常に重要です。「部屋の広さが思ったより狭かった」「リフォームが必要に感じた」などの声は、次の改善点につながります。積極的に聞き取りを依頼しておきましょう。
価格設定と販売戦略の見直し
売却が長引く原因の多くは「価格設定」にあります。
例えば査定額が3,000万円と出ても、実際に売れる価格は市場の需要によって前後します。売却活動を始めて3か月経っても動きがなければ、価格を見直すタイミングです。
ただし「一気に値下げする」のではなく、100万〜200万円単位で段階的に調整するのがおすすめです。値下げは買主に「今がチャンス」と思わせる効果がある反面、大幅すぎると「売れ残り感」を与えるリスクもあります。
販売戦略の見直しも忘れてはいけません。
- 写真の撮り直し(明るさや構図で印象は大きく変わる)
- 広告媒体の追加(大手ポータルサイト・地域密着サイトの両方を活用)
- 内覧時の演出(整理整頓、簡単なリフォーム、香りや照明の工夫)
ちょっとした改善が売却のスピードを変えることもあります。
複数社比較と契約更新の判断基準
媒介契約の期間は通常3か月です。売却が進まないまま契約更新の時期を迎えたら、そのまま継続するか、他社に切り替えるかを判断する必要があります。
判断の基準としては、次の3つがポイントです。
- 販売活動の実績
問い合わせ件数や内覧件数はどれくらいあったか?報告内容は具体的だったか? - 提案力
価格や戦略の見直しについて積極的に提案してくれたか?ただ「様子を見ましょう」と言われていないか? - 相性
担当者とスムーズに意思疎通ができたか?こちらの疑問に誠実に答えてくれたか?
この3点を冷静に振り返ることで、継続するか乗り換えるかの判断がしやすくなります。実際に「別の会社に切り替えたらすぐに売れた」という事例も珍しくありません。
不動産売却は「待つだけ」ではうまくいきません。
- 担当者と密にコミュニケーションを取る
- 適切な価格設定と販売戦略を調整する
- 契約更新のたびに冷静に振り返る
この3つを意識すれば、売却のスピードも条件もぐっと良くなるはずです。
あなたは今の売却活動にどれだけ納得できていますか?もし少しでも疑問や不満があるなら、今回のポイントを参考に改善に踏み出してみてください。よくある質問とトラブル回避のヒント
不動産売却を進める中で、誰もが一度は抱く疑問があります。特に「売れなかった場合どうなるのか」「契約期間中でも他社にお願いできるのか」といった不安は大きいですよね。ここでは、よくある質問を取り上げながら、トラブルを避けるための考え方を整理します。
「売れなかったら違約金はある?」
結論から言うと、売れなかっただけでは違約金は発生しません。
不動産会社の仲介手数料は、売買契約が成立したときに初めて支払うものだからです。媒介契約を結んで広告を出しても、売れなければ報酬はゼロ。不動産会社にとってはリスクを負って活動している形になります。
ただし注意したいのは、売主都合でキャンセルした場合です。
たとえば「やっぱり売るのをやめた」「家族の意向で中止した」といったケースでは、買主と売買契約を結んだ後なら違約金や手付金の返還義務が発生します。金額は契約内容次第ですが、数百万円単位になることもあります。
つまり、売れなかっただけなら違約金はないものの、一度契約を結んだ後の撤回にはリスクがあるということです。契約前に「解約時の取り扱い条項」を必ず確認しておきましょう。
「契約期間中に他社へ切り替えられる?」
媒介契約の期間は原則3か月です。この間は基本的に他社と同時契約はできません(一般媒介を除く)。
ただし、契約期間中でも売主の意思で契約を解除することは可能です。違約金がかかることはほとんどありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 既に広告費や特別な販促費を実費精算すると定められている場合は、その分を請求される可能性がある
- 契約解除は口頭ではなく、書面で行って証拠を残すのが安心
- 契約を切り替える理由を明確にしておくと、後々のトラブルを避けやすい
実際のところ、「活動状況が不十分だから他社に乗り換えたい」という理由で契約解除するケースは珍しくありません。不動産会社としても、契約を無理に引き止めることはできません。
不動産売却では、「違約金がかかるのでは?」「契約途中で動けないのでは?」という誤解から、行動をためらう人が多いです。しかし、契約書の条項を理解していれば、大きなトラブルは防げます。
あなたが今売却を進めているなら、「解約時の取り扱い」と「契約更新の条件」の2点をぜひ確認してみてください。それだけで安心感が大きく変わるはずです。