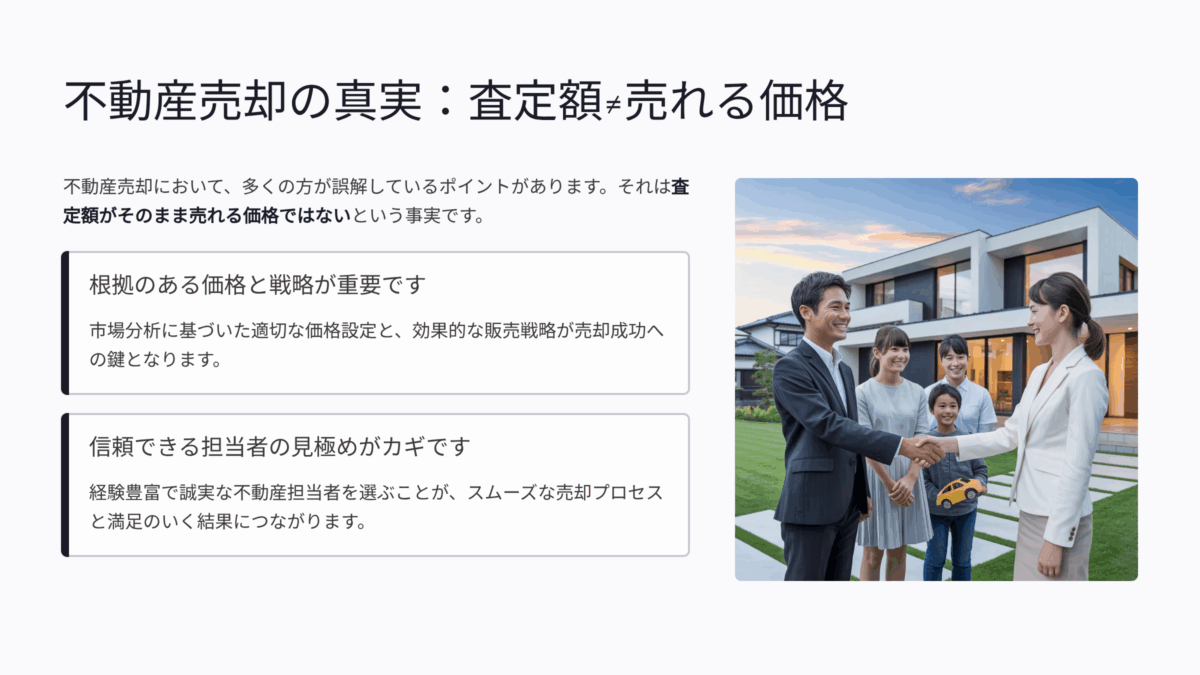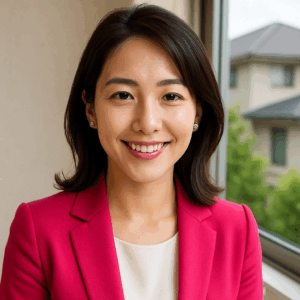
「高めの査定額」に期待しすぎて失敗する人、実はかなり多いんです。本当に売れる価格との違い、どう見分ければいいのでしょうか?目次を見て必要なところから読んでみてください。
なぜ「高めの査定」に注意が必要なのか?【不動産売却の落とし穴】
査定額=売却価格ではない!その理由とは?
不動産売却を考え始めたとき、最初に気になるのが「いくらで売れるのか?」という点ですよね。
特に一括査定サイトを使うと、わずか数分で複数社から「査定額」が届き、目を引くのはやはり一番高い金額。
「え?こんなに高く売れるの?」
「この会社、すごく頑張ってくれそう!」
「じゃあ、ここにお願いしてみようかな?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
でも、ちょっと待ってください。
その査定額、本当に売れる金額でしょうか?
結論から言えば、査定額はあくまで予測であり、実際に売れる価格とは異なります。
なぜなら、不動産の価格は「需要と供給のバランス」で決まるものであり、いくら売主が高く売りたいと望んでも、買主が納得しない価格では取引が成立しないからです。
たとえば、あなたが中古車を売るとしたら、業者が「150万円で売れると思います」と言っても、実際に買い手が現れなければ意味がありませんよね?
それと同じことが、不動産の世界でも起こります。
では、なぜこんなにも高めの査定額が提示されるのでしょうか?
なぜ不動産会社は高めの査定額を提示するのか
答えはシンプルです。
「選ばれるため」です。
一括査定サイトでは、複数の不動産会社が競って査定額を提示します。
売主であるあなたは、当然「より高く売ってくれそうな会社」を選びたくなりますよね。
不動産会社もそれを分かっているため、現実より少しでも高めに査定額を出すことで、他社より目立とうとするのです。
もちろん、すべての不動産会社がそうしているわけではありません。
中には誠実な見積もりを出してくれる会社もありますし、戦略的に「高く売れる工夫」をしてくれる会社もあります。
ですが、査定額を競うこと自体が目的化してしまっている会社も存在するのは事実です。
実際にあった事例をご紹介しましょう。
高すぎる査定額が招く売却トラブルの実例
ある40代のご夫婦が住んでいた築20年の戸建住宅。
一括査定サイトを通じて査定を依頼したところ、
A社:2,800万円
B社:2,950万円
C社:3,300万円
当然、C社に惹かれて媒介契約を結びました。
しかし、実際に販売を始めてみると、2ヶ月経っても1件の問い合わせすら入らない。
内覧どころか、反響ゼロのまま3ヶ月が過ぎてしまいました。
最終的には価格を何度も下げ、最終売却価格は2,700万円。
しかも、時間がかかった分、次の住み替え先の購入タイミングもズレてしまい、ローンの二重払いを余儀なくされたそうです。
このケースの問題点は何でしょうか?
- 最初に提示された高すぎる査定額を信じてしまった
- 不動産会社が販売活動に熱心ではなかった
- 適正価格よりも高く売り出したため、市場からスルーされた
このように、「高めの査定額」は一見すると魅力的ですが、かえって売却のチャンスを逃してしまうリスクもあるのです。
一方で、反対意見として「でも、高く査定してくれた方が、売る気になれるじゃない?」という声もあります。
たしかに、モチベーションアップにつながる面もありますし、粘り強い販売戦略があれば、高値成約も不可能ではありません。
しかし、そのためには相応の戦略と時間、そして優秀な担当者の存在が不可欠です。
それらが伴っていない「高値査定」は、単なる見せかけの数字になってしまうのです。
高めの査定額に惑わされないためには?
では、どうすれば高すぎる査定額に惑わされず、現実的な売却価格を見極められるのでしょうか?
✅ 複数社の査定を比較する(最低3社)
✅ 机上査定だけでなく、必ず訪問査定も受ける
✅ 過去の成約事例や相場データを確認する
✅ 「なぜこの査定額になるのか」の根拠を聞く
これらを意識するだけでも、査定額と実際の売却価格とのギャップを減らすことができます。
加えて、「この金額で売れると断言できますか?」と担当者に尋ねてみるのもおすすめです。
その答え方で、その会社の誠実さや経験値も見えてくるでしょう。
不動産売却は、人生の中でも数少ない大きな取引です。
だからこそ、数字だけを見て判断するのではなく、「なぜその価格なのか?」を理解して納得できる売却戦略を立てることが大切です。
高めの査定額に惑わされず、冷静に比較し、判断する。
それが、後悔しない不動産売却への第一歩だと、私は思います。
査定額の種類と精度の違い【机上査定と訪問査定の理解】
不動産の査定を依頼する際、多くの人が最初に目にするのが「机上査定」。
そして、その次のステップとして案内されるのが「訪問査定」。
この2つの査定方法、名前は知っていてもその違いや使い分け方を正確に理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
「どちらを選べばいいの?」
「机上査定の数字って信用していいの?」
「訪問査定って何を見られるの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
ここでは、査定額の算出方法とその精度について、具体的な違いと注意点をわかりやすく解説していきます。
机上査定:気軽だがズレが大きい?
机上査定とは、実際に物件を見ずに、インターネット上や書類上の情報のみを使って出される査定のことです。
たとえば、以下のようなデータをもとに算出されます。
| 机上査定で使われる主な情報 |
|---|
| 住所(エリア特性) |
| 土地・建物の面積 |
| 築年数 |
| 間取り |
| 周辺の成約事例・相場 |
とても手軽でスピーディーなのが魅力で、最近はLINEで完結するサービスもありますよね。
ただし、ここが落とし穴。
机上査定はあくまで「理論上の価格」にすぎません。
なぜなら、以下のような要素は一切考慮されていないからです。
- 建物の傷み具合
- リフォーム歴
- 接道状況や陽当たり
- 周辺の騒音や環境
たとえば、同じ築20年の戸建てでも、外壁の塗装や水回りのリフォームを定期的に行っていれば、見た目も印象も大きく変わりますよね。
ところが机上査定では、そうした差を反映することができないのです。
つまり、机上査定は参考程度の“入り口”でしかないということ。
気軽に目安を知りたいときには便利ですが、「この価格で売れる」と思い込んでしまうと、後でギャップに苦しむことになります。
訪問査定:現地調査で精度が上がる理由
一方、訪問査定は、不動産会社の担当者が実際に現地に足を運び、物件の状態を直接チェックして査定額を出す方法です。
これは、いわば現実に即した“体感値ベースの査定”。
机上査定と比べて、格段に精度が高くなります。
担当者は以下のようなポイントを確認します。
- 外壁や屋根の劣化具合
- 室内の清潔感やメンテナンス状況
- 日当たりや風通し
- 周辺環境(騒音・交通量・隣地の状態)
- 境界の明確さ
- 駐車場の有無と利便性
これらはすべて、購入希望者が「この家を買いたいかどうか」を判断するうえで極めて重要なポイント。
つまり、市場の実態に近い価格が導き出せるということです。
ちなみに、不動産会社側としても訪問査定は“本気度”が伝わるポイント。
売却に真剣な売主に対して、販売戦略まで踏み込んだアドバイスをしてくれる可能性が高まります。
訪問査定のチェックポイントとは?
では、訪問査定ではどのような視点で物件を見られているのでしょうか?
「どこを見られてるのか気になる…」という方も多いと思いますので、以下に担当者が実際にチェックするポイントをまとめてみました。
| チェックポイント | 担当者が見ている視点 |
|---|---|
| 建物の外観 | 外壁や屋根の劣化、ヒビ割れの有無 |
| 室内の状態 | フローリングやクロスの汚れ・傷み |
| 水回りの設備 | 経年劣化・リフォーム歴の有無 |
| バルコニー・庭 | 整理整頓・雑草の管理状態 |
| 接道状況 | 道路幅、車の出入りしやすさ |
| 周辺環境 | ゴミ置き場、騒音、隣地の建物 |
特に意外と見落としがちなのが、「臭い」「音」「生活感」といった数値化しにくいポイントです。
これらは買主の印象を大きく左右するため、査定額にしっかり反映されます。
ですから、訪問査定の前には簡単な掃除や整理整頓をしておくと印象がグッと良くなります。
わざわざリフォームまでする必要はありませんが、「大切に住んできた感」が伝わる状態を意識することが大切です。
まとめ:どちらの査定にも意味はある、でも…
机上査定と訪問査定は、役割も精度もまったく異なる査定方法です。
- 机上査定は「目安価格を知る」ための第一歩
- 訪問査定は「本当に売れる価格」を知るための現地確認
不動産の売却は、安くても後悔、高すぎても売れ残り。
だからこそ、正しい査定を受けて「納得のいく価格」で売ることが一番大切なんですよね。
机上査定だけで判断するのではなく、ぜひ一歩進んで訪問査定を受けてみてください。
きっと、あなたの不動産の「本当の価値」が見えてくるはずです。
一括査定サイト利用時の注意点【メリットとリスク】
不動産を売ろうと考えたとき、まず候補にあがるのが「一括査定サイト」ではないでしょうか?
住所や面積、築年数などを入力するだけで、複数の不動産会社から査定額が届く――。
この便利さに「すごくラクそう!」と思われた方、多いのではないでしょうか?
たしかに、効率的です。しかも無料。
でもその一方で、「甘い査定額」に引っかかってしまったり、連絡ラッシュで疲弊したりするケースも少なくありません。
「高い査定額=信頼できる会社」ではないとしたら?
「一括査定を使ったのに、結局どこも信用できなかった…」となったら?
今回は、一括査定サイトのメリットとリスクを整理しながら、後悔しないための使い方を一緒に考えていきましょう。
一括査定は便利!だが「甘い査定額」に注意
まず大前提として、一括査定サイトは非常に便利なツールです。
✅ 一度の入力で複数社に依頼できる
✅ 自宅にいながら相場観がつかめる
✅ 不動産会社の対応力を見比べられる
とくに「どこの会社に相談すればいいかわからない…」という方にとっては、第一歩を踏み出す手助けになるのは間違いありません。
しかし、ここで注意しておきたいのが、提示される査定額が“高め”に出やすいという特性です。
なぜなら、複数の会社が競い合う構造上、
「高めの金額を提示すれば、売主に選ばれる可能性が高い」
という心理が働くからです。
実際、筆者がサポートした売主の中には、こんなケースがありました。
📌 ケース例:机上査定で3,800万円と提示されたが…
ある中古マンションを査定したところ、A社は3,800万円、B社は3,550万円。
当然、高く売ってくれると思ったA社に依頼しましたが、3ヶ月たっても1件も内覧が入らず。
最終的に売却できたのは3,400万円でした。
後からわかったのは、A社は他社よりも相場より高めの査定を常に出す方針だったということ。
つまり、売却戦略よりも“案件を取ること”が目的だったのです。
「え?じゃあ、一括査定サイトって意味ないの?」
と思われたかもしれませんが、決してそうではありません。
大切なのは、査定額そのものではなく、「なぜその金額になったのか」の根拠を確認することです。
- 成約事例を提示してくれたか?
- 近隣の販売状況と比較しているか?
- 価格の下限・上限も説明してくれたか?
こういった説明があるかないかで、その会社の誠実さは見えてきます。
依頼は何社まで?対応できる範囲で絞るのがコツ
一括査定サイトの中には、最大10社に同時依頼可能というサービスもあります。
「多ければ多いほどいいのでは?」と思いがちですが、ここにも落とし穴があります。
実際に査定依頼を出すと、以下のような対応が一斉に始まります。
- 各社から電話・メールでの連絡
- 訪問査定の日時調整
- 売却希望のヒアリング
最初は「比較検討したいだけだったのに…」と感じる方も少なくありません。
しかも、一括査定に登録した情報は共有されるため、電話が鳴り止まないというケースも。
対応に追われて疲れてしまい、
「もう面倒だから最初に電話をかけてきた会社でいいや…」
となってしまうと、本末転倒ですよね。
では、何社に依頼するのがベストなのでしょうか?
✅ 目安は3〜5社まで
✅ そのうち2〜3社に訪問査定を依頼する
✅ 対応の質を見極めながら1社に絞る
このステップを踏むことで、負担を抑えつつ、比較しやすくなります。
また、「このくらいなら自分でも対応できそう」と感じる範囲で依頼するのが一番です。
本当に信頼できる不動産会社の見極め方
では、数ある不動産会社の中で、どのようにして「信頼できる1社」を選べばよいのでしょうか?
査定額だけでなく、以下のような対応姿勢や提案力を見ることをおすすめします。
| 評価ポイント | チェックすべき対応内容 |
|---|---|
| 査定根拠の明確さ | 成約事例・市場動向を丁寧に説明してくれる |
| 売却戦略の具体性 | 価格設定や広告手段、販売スケジュールがある |
| 担当者の誠実さ | 質問に丁寧に答える、売却を急かさない |
| コミュニケーション | 連絡のタイミング、言葉遣い、対応の柔軟さ |
一方で、以下のような対応が見られたら注意が必要です。
- 査定額の根拠が曖昧、または強引に高く出す
- 「今決めないと売れませんよ」と急がせてくる
- 他社の悪口ばかり言う
- 担当者が頻繁に変わる
これらは、売主の不安を煽って契約を取ろうとする典型的なパターンです。
“売るための話し方”と、“寄り添うための話し方”は、聞けばすぐにわかります。
まとめ:一括査定サイトは「使い方次第」で強力な武器になる
一括査定サイトには、メリットもあればリスクもあります。
しかし、使い方を間違えなければ、不動産売却の第一歩として非常に有効なツールです。
- 査定額に一喜一憂せず、その根拠を確認する
- 対応できる範囲で会社を絞って依頼する
- 提案力・誠実さを重視して比較する
この3つの視点を持つだけで、「騙された」「失敗した」と感じる可能性はグッと下がります。
あなたの大切な不動産を、納得いく価格で売却するために――
数字だけでなく、“人”を見極める目を持つことが、最も確実な方法かもしれませんね。
本当に売れる価格の見極め方【相場・事例・プロの視点】
「査定額は高かったのに、全然売れなかった…」
「“相場”って聞くけど、具体的にどう見ればいいの?」
こんな声、実際に売却経験者からよく聞きます。
不動産の価格は「売主の希望」ではなく、「買主の納得」で決まるもの。
つまり、売却成功のカギは“見込み価格”ではなく“実際に売れた価格”にあるということです。
ですが、初めての売却では、何を基準にすればよいのか、なかなかわかりませんよね。
ここでは、成約事例・査定額との乖離・複数社比較という3つの視点から、「本当に売れる価格」を見抜く方法をわかりやすく解説していきます。
成約事例から読み解く「売れる価格」の相場観
まず、最も信頼性のある「価格の物差し」は、成約事例です。
つまり、すでに売買が成立した不動産の実績価格。
なぜなら、「いくらで売れたか」は、市場が“その価値を認めた価格”だからです。
たとえば、「似たような築年数・広さ・立地の物件が3,500万円で成約していた」という情報があれば、それがその地域の実勢価格だと見なされます。
✅ 国土交通省「土地総合情報システム」
✅ レインズマーケットインフォメーション
✅ 民間サイトの「過去の販売履歴」
これらを活用することで、過去の売買価格をある程度把握できます。
もちろん、「うちの家はリフォームしてるから、もう少し高く売れるはず」と思う気持ちもわかります。
ただ、その思い込みだけで価格設定してしまうと、相場からズレて売れ残るリスクがあるんですよね。
ですから、まずは「現実に売れた価格」を基準に考えることが、ブレない売却戦略の第一歩です。
査定額と売却実績の乖離に注意
さて、ここで気をつけたいのが「査定額=売れる価格」ではないという点。
むしろ、実際にはこの2つが大きくかけ離れているケースが少なくありません。
たとえば、こんな経験はないでしょうか?
- 机上査定で4,000万円と出たのに、実際には3,400万円でしか売れなかった
- 訪問査定で「3,800万はいけます」と言われたが、案内すら入らなかった
こうしたズレは、査定時に「売主の期待に寄せた価格」を提示していることが多いからです。
つまり、査定はあくまでも「目安」であり、契約書に書かれる保証価格ではないということ。
ここで大切なのは、以下の2点をしっかり見極めることです。
| 見極めポイント | 内容 |
|---|---|
| 査定根拠の有無 | 「周辺相場」「成約実績」「販売期間」などの説明があるか |
| 販売戦略の整合性 | 査定額に見合った広告戦略や価格調整の方針が提示されているか |
また、不動産会社によって査定の根拠や考え方は違います。
ですから、査定額の高さに一喜一憂するのではなく、「この金額が現実的かどうか」を冷静に見て判断することが求められます。
複数社の査定結果を比較するポイント
では、どうすれば「売れる価格」に近づけることができるのでしょうか?
結論から言えば、複数社に査定を依頼し、それぞれの視点を比較することです。
ただし、ここでも注意すべきポイントがあります。
単純に「一番高いところが正解」と考えるのは早計。
比較すべきは、「金額」ではなく「提案内容」と「根拠の深さ」です。
以下のような視点で比較してみましょう。
| 比較項目 | 確認すべき内容 |
|---|---|
| 査定価格の妥当性 | 周辺の成約事例との整合性があるか |
| 提案の内容 | 売出価格・タイミング・広告手法が明示されているか |
| 担当者の対応 | 誠実さ、レスポンス、説明の分かりやすさ |
| 会社の実績 | 地域での販売経験・過去の成約データの提示有無 |
そして何より大切なのが、「この人なら任せられる」と思える担当者かどうか。
結局、どんなにデータがそろっていても、売却の成否は「人」によって大きく左右されるからです。
まとめ:「売れる価格」は“数字の勝負”ではなく“納得の勝負”
不動産売却で後悔しないためには、
高すぎず、安すぎず、買主が納得してくれるラインを見極めることがカギになります。
- 成約事例をベースにする
- 査定額とのズレを冷静に見る
- 複数社の視点から価格と戦略を見比べる
こうした積み重ねの先に、“本当に売れる価格”が見えてくるはずです。
そして何より、売主であるあなた自身が、その価格に納得できているかどうか。
最終的には、「売れてよかった」と思えるゴールを迎えられることが、何より大切なんじゃないかなと思います。
査定額に惑わされない!売却成功のための行動ステップ
「この家、◯◯万円で売れますよ!」
そんな言葉を聞くと、どうしても期待してしまいますよね。
ですが、売却の成否は“数字”だけで決まるものではありません。
査定額が高い=成功ではない。
むしろ、どんな売却戦略を立てるか、誰に任せるか、そして自分がどう動くか。
こうした要素の積み重ねこそが、最終的な成功に直結するのです。
ここでは、「査定額に振り回されない」ために、売主として何を意識し、どんな行動を取るべきか。
そのステップを、順を追って解説していきます。
売却戦略は価格だけで決まらない
「とりあえず高く出して、様子を見よう」
「反応がなかったら、あとで値下げすればいい」
そう考える方、意外と多いです。
でも実際は、最初の売出価格が“売れるかどうか”を大きく左右するということ、ご存知でしょうか?
というのも、買主は物件情報が出たタイミングで最も注目するからです。
そのときに価格が高すぎると、
「高いな、他を見よう」となってスルーされ、
その後いくら値下げしても、“売れ残り感”が出てしまうんですよね。
つまり、価格はあくまでも戦略の一部。
本来、以下のような全体設計があってこそ、はじめて“売れる仕組み”が成立します。
✅ 価格設定(相場とのバランス)
✅ 売出時期の見極め(季節・市場動向)
✅ 広告戦略(写真・キャッチコピー)
✅ 内覧対応の準備(印象・清掃・香り)
✅ 値下げのタイミングと幅
不動産の売却は、マーケティングです。
「言われた通りに任せておけば売れる」ではなく、売主自身も戦略の一員として関わることが重要なのです。
信頼できる営業担当者を見極める質問例
売却がうまくいくかどうかは、営業担当者の力量に大きく左右されるといっても過言ではありません。
査定額や会社の知名度よりも、「誰が担当してくれるか」のほうがずっと重要です。
では、どうやって見極めればいいのか?
ここでは、初回面談や訪問査定の際に使える「見極め質問例」をご紹介します。
| 質問例 | 見極めポイント |
|---|---|
| 「このエリアで過去に売却経験はありますか?」 | 地域の相場感・提案力 |
| 「過去の販売実績で印象に残っている案件は?」 | 経験値・戦略の幅 |
| 「この価格で売れる根拠は何ですか?」 | 査定の信頼性 |
| 「値下げする場合、どのように判断しますか?」 | 価格調整の方針 |
| 「他社と比較して、御社の強みは何ですか?」 | 差別化ポイントの明確さ |
| 「販売期間中、どのように報告してもらえますか?」 | コミュニケーション力 |
これらの質問に対して、丁寧に、かつ論理的に答えてくれる担当者であれば、安心して任せられる可能性が高いです。
逆に、曖昧な回答や極端に楽観的な話ばかりする担当者には注意が必要かもしれません。
「売るために甘い話をしているだけ」という可能性もあるからです。
売却までのロードマップと判断基準
最後に、実際に売却を進める上での行動ステップと判断のポイントを確認しておきましょう。
| ステップ | 主な内容 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| ① 情報収集 | 相場・制度・税金を調べる | 情報は複数ソースから確認 |
| ② 一括査定 | 複数社に机上査定を依頼 | 査定額の理由を聞く |
| ③ 訪問査定 | 上位2~3社に依頼 | 提案力・担当者の相性を見る |
| ④ 媒介契約 | 1社と契約(専任or一般) | 担当者との信頼性がカギ |
| ⑤ 売出準備 | 写真撮影・清掃・書類確認 | 見せ方の工夫が重要 |
| ⑥ 販売活動 | 広告・内覧・問い合わせ対応 | 反応がないときは見直しを |
| ⑦ 価格調整 | 状況を見て価格再設定 | タイミングを見極める |
| ⑧ 成約・引渡し | 契約→決済・引渡しへ | 条件確認をしっかりと |
このように、価格だけでなく、プロセス全体に納得しながら進めることが成功への近道です。
迷ったときは、「なぜそれをするのか?」「この選択で何が変わるのか?」を自分に問いかけてみてください。
その答えが見つかったとき、不動産売却は“ただの取引”ではなく、納得と満足を生む経験に変わるはずです。
売却成功のカギは、目先の数字に振り回されず、「長期的な視点」で一つ一つの判断を重ねていくこと。
“誰と売るか”“どう売るか”に目を向けることで、きっと後悔しないゴールに近づけるはずです。
よくある質問Q&A:高めの査定に関する疑問を解決!
ここまで「高めの査定には注意が必要」と繰り返しお伝えしてきましたが、それでもやっぱり気になるものですよね。
「でも、高い査定で売れたらラッキーなんじゃ?」
「値下げしないで済むコツはないの?」
「じゃあ、査定額ってどこまで信じていいの?」
そんな“心の中のモヤモヤ”に、ここで一つずつ答えていきます。
高めの査定でも売れる場合はある?
結論から言うと、高めの査定でも売れることはあります。
ただし、いくつかの条件がそろっている必要があります。
✅ 相場より明らかに希少性がある(角地・南向き・駅近など)
✅ 物件の状態が非常に良く、リフォーム済み
✅ 近隣で類似物件が供給不足になっている
✅ タイミング的に買主の需要が高まっている(例:春先)
つまり、「たまたま高く売れた」のではなく、“売れる根拠があるかどうか”がすべてなんです。
もし高めの査定を提示された場合は、こう問いかけてみてください。
「この金額で売れた実例、ありますか?」
「この価格に納得して買う人が、今の市場にどれくらいいますか?」
納得できる答えが返ってくるなら、その価格は「挑戦価格」として価値があります。
でも、そうでなければ、むしろ売れ残って値下げするリスクのほうが高いかもしれません。
値下げ交渉を避けるための工夫とは?
「できれば、値下げせずに売りたい」
これは誰しもが思うことですよね。
では、そのために何ができるか?
実は、いくつかの“準備と工夫”で、値下げのリスクを減らすことは可能です。
✅ 売出価格の設定を慎重に行う
市場相場より大きく乖離しない価格設定が基本です。
“ギリギリ届きそうなライン”を見極めるのがプロの仕事です。
✅ 内覧時の印象を良くする
部屋を片付け、生活感を少し抑えるだけで、印象はガラッと変わります。
照明を明るくしたり、香りに気を配ったりといった工夫も効果的です。
✅ 買主の不安要素を先に潰しておく
「境界は明確ですか?」「リフォーム履歴は?」
こうした質問に即答できるよう、必要書類を準備しておきましょう。
✅ 信頼できる担当者と連携する
価格交渉に対して、どう対応するかは営業担当の腕次第でもあります。
「値下げは必要か?」「譲歩のタイミングはいつか?」など、
戦略を事前に共有しておくと安心です。
つまり、“値下げ交渉されにくい売り方”を意識することが、最終的な価格のキープにつながるんですね。
査定額を鵜呑みにしないためのチェックリスト
最後に、「この査定額、信じても大丈夫?」を見極めるためのチェックリストをご紹介します。
これを使えば、査定結果の“真偽”を冷静に判断できるはずです。
✅ 査定額の根拠が、成約事例・相場に基づいて説明されている
✅ 周辺の販売中物件と比較して、大きく乖離していない
✅ 「売れる価格」と「売出価格」の違いを説明してくれる
✅ 相場より高めでも、「売るための戦略」まで提案がある
✅ 価格以外のアドバイス(売出時期・広告戦略など)もある
✅ 値下げの可能性と、その対応方法についても話してくれる
このうち、4つ以上当てはまれば“信用できる査定”の可能性が高いと言えるでしょう。
逆に、査定額だけを強調し、根拠や説明が曖昧な会社は要注意です。
最後に:数字に踊らされず、納得して進むことが何より大切
査定額に一喜一憂する気持ち、よくわかります。
でも本当に大切なのは、「その金額で誰が買うのか?」「そのプロセスに納得できるか?」ということ。
高く売れるかどうかは、市場が決めること。
でも、どう売るか、誰に任せるか、どこまで納得して進めるかは、あなた自身が決められることです。
あなたの売却が、「納得」と「満足」のある経験になりますように。