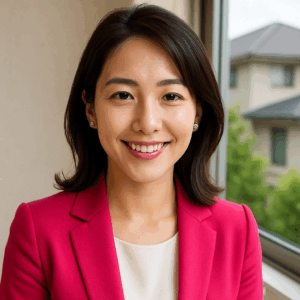
金利上昇で家が売れにくくなるって本当?背景や市場への影響、売却成功のコツまで徹底解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
金利上昇で家が売れなくなるって本当?【背景と基本知識】
あなたは「金利が上がると家が売れにくくなる」という話を聞いたことはありますか?
ニュースや不動産サイトでも、2024年から2025年にかけて住宅ローン金利がじわじわと上昇していると報じられています。
では、本当に金利が上がるだけで家が売れなくなってしまうのでしょうか?
そもそも金利と住宅市場はどう関係しているのか。なぜ金利の動きが売れ行きに影響するのか。そして2025年の住宅ローン金利はどうなりそうなのか。
今回は、この3つを軸に「金利上昇と不動産市場の関係」をわかりやすく解説していきます。
目次
- 金利が上がると住宅市場にどんな影響が出る?
- なぜ金利上昇で不動産が売れにくくなるのか
- 2025年の住宅ローン金利動向と市場の変化
金利が上がると住宅市場にどんな影響が出る?
金利上昇は、住宅市場にとって「見えない値上げ」のようなものです。
例えば3,500万円の住宅ローンを35年固定で組んだ場合、金利が1%から2%に上がると、毎月の返済額はおよそ1万6,000円以上増えます。年にすれば約20万円、35年間では700万円近い負担増。数字で見るとインパクトが大きいですよね。
返済額が上がると、住宅ローン審査に通る人の数も減ります。つまり、同じ年収の人でも「買える家の価格」が下がるのです。
結果として、住宅市場では次のような変化が起こりやすくなります。
- 購入希望者の予算が下がる
- 高額物件の売れ行きが鈍る
- 中古物件や小規模住宅への需要がシフト
特に都市部の新築マンションや人気エリアの戸建ては、価格が高止まりしている傾向にあり、金利上昇の影響を強く受けやすい状況です。
なぜ金利上昇で不動産が売れにくくなるのか
理由はシンプルに「買える人が減るから」です。
しかし背景をもう少し深く見ると、3つの要因が絡み合っています。
- ローン負担増による購買意欲の低下
住宅購入者のほとんどがローンを利用します。金利が上がると月々の支払いが増え、心理的にも「今は買わないほうがいいかな」と慎重になる人が増えます。 - 審査基準の厳格化
金融機関は返済比率(年収に占めるローン返済額の割合)を重視します。金利が高いと同じ借入額でも返済比率が上がり、審査に通らないケースが増えます。 - 市場全体の値下げ圧力
売主は「売れない」状況が続くと価格を下げざるを得ません。結果的に市場全体で価格調整が進み、売却を急ぐ人はさらに条件を下げざるを得なくなります。
私が不動産業界で見てきた中でも、金利上昇局面ではまず新築市場の動きが鈍り、その後中古市場に影響が波及していくのが一般的です。特に売却を急いでいる人ほど、価格交渉に応じざるを得ない場面が増えます。
2025年の住宅ローン金利動向と市場の変化
2024年後半から日本銀行は長期金利の上昇をある程度容認する姿勢を見せており、金融機関も固定型住宅ローンの金利をじわじわと引き上げています。
2025年は以下の傾向が予想されます。
- 固定金利はさらに上昇傾向
特に35年固定は0.1~0.3%程度の上昇が続く見込み。 - 変動金利は当面低位だが将来的リスクあり
短期金利は急には上がらないものの、長期的には上昇圧力がかかる可能性。 - 買い控えの長期化
「もっと下がるかも」「様子を見たい」という心理で市場全体の動きが鈍化。
こうした金利環境下では、買い手にとっては慎重になる理由が増え、売り手にとっては戦略が求められます。
例えば、売却前にリフォームで付加価値をつけたり、価格設定を市場相場より少し下げて早期売却を狙うなどです。
まとめ:行動のタイミングを見極めよう
金利上昇は避けられない市場の波ですが、「だから売れない」と決めつける必要はありません。
むしろ、金利が上がる局面こそ買い手の動きを正しく読み、売却戦略を柔軟に変えることが重要です。
- 高額物件は価格調整やリフォーム提案で差別化
- 購入者層を絞り、ターゲットに合った広告戦略を取る
- 複数の不動産会社から査定を取り、現実的な売却価格を把握する
「待つ」のも戦略の一つですが、不動産はタイミングと条件の掛け算で結果が変わります。
今の金利動向を踏まえ、自分の状況に合った売却の動きを早めに検討しておくことをおすすめします。
実際に金利上昇で売却が難航した事例【経験談から学ぶ】
金利の上昇はグラフや数値で見ると抽象的ですが、実際に売却活動をした方にとっては非常に現実的な「壁」になります。ここでは私が不動産業界で関わった、もしくは耳にした中でも印象的だった3つの事例をご紹介します。きっと「自分ならどう動くか?」を考えるヒントになるはずです。
売却予定だったが買い手がつかず価格を見直した事例
東京都内の築12年のマンション。売主は当初5,480万円で売り出しを開始しました。金利は当時1.2%ほどでしたが、売却活動を始めて2カ月後には固定型で1.5%に上昇。
一見わずかな上昇ですが、ローン借入額が大きい買い手層にとっては月1万円以上の返済増。結果、内覧予約は入るものの「もう少し安い物件を探します」という声が続きました。
売主は迷った末、3カ月目に5,280万円に値下げ。そこから2週間で契約成立。
「もっと早く価格見直しすればよかった」と振り返っていました。金利上昇期は、売り出し価格の柔軟性がカギだと痛感したケースです。
売却期間が延びた結果、ローン残債と釣り合わなくなった事例
地方都市で築8年の戸建を売却予定だったAさん。住宅ローン残債は2,800万円、売却想定価格は3,000万円でした。
しかし金利上昇が報じられる中、買い手の予算感が下がり、半年経っても成約に至らず。ようやく買い手が現れたときには市場相場が落ち着き、査定価格は2,700万円に。
結果、売却後も100万円以上のローン残が残り、貯金を切り崩して返済することに。
「もっと早く動いていれば残債をなくせたのに」とAさんは話します。売却期間の長期化は、金利上昇局面では特にリスクになる典型例です。
高めに売り出したが価格調整でようやく売却できたケース
Bさんは駅徒歩5分の好立地マンションを所有。周辺相場よりも高い4,800万円で売り出しました。
当初は「立地が良ければ高くても売れる」と踏んでいたのですが、金利上昇の影響で買い手がローンの借入額を抑える傾向に。半年間問い合わせはあったものの、購入申し込みには至らず。
そこで思い切って4,600万円に価格を下げたところ、1カ月以内に成約。
Bさんいわく「高く売りたい気持ちは誰でもあるが、金利環境が変わると相場の“天井”が下がる」という現実を学んだそうです。
この3つの事例に共通するのは、「金利上昇に伴い買い手の条件が厳しくなる」こと。そして価格調整のタイミングを逃すと、売却期間が延び、結果的に条件が悪化するということです。
売り手としては、市場の動きを見ながら柔軟に戦略を変えることが欠かせません。
金利上昇下でも売れる家の特徴とは?
「金利が上がれば、家は全部売れにくくなるんじゃないの?」
そう思われるかもしれませんが、実際には金利上昇局面でもスムーズに売れる家があります。
違いを生むのは、立地や物件の状態、そして“買いたい理由”に直結する魅力があるかどうかです。
立地・築年数・管理状態の良さが与える影響
不動産の価値は「場所・築年数・状態」でほぼ8割が決まる、と言われます。
特に金利が上がった時期には、買い手は「どうせ同じローンを払うなら条件の良い物件を」と選別を厳しくします。
- 駅徒歩10分以内の物件:通勤・通学の利便性が高く、買い手の数が減りにくい
- 築10年以内の物件:住宅ローン減税や修繕リスクの低さが魅力
- 管理状態が良好なマンション:外観や共用部の清潔感が購入判断を後押し
私が仲介に入った案件でも、築8年・駅徒歩5分・管理組合が活発なマンションは、同時期に周辺の築20年以上の物件が売れ残る中、3週間で成約しました。見に来た人の第一声が「管理が行き届いてますね」だったのが印象的です。
購入希望者のニーズに合致した物件とは
金利上昇期には、買い手の予算はシビアになります。そのため、予算内で“自分に合う”と思わせる要素があるかどうかがカギです。
- 子育て世帯向け:学区・公園・商業施設の近さ
- 高齢者・セカンドライフ層:段差の少ない間取り・医療機関へのアクセス
- 単身・共働き世帯:駅近・防犯設備・宅配ボックスなど利便性重視
この“合致”は価格だけでは決まりません。「この家で暮らすイメージが湧くかどうか」が成約率を左右します。
金利上昇でも需要が下がらない物件ジャンル
不思議に思うかもしれませんが、金利が上がっても動きが鈍らないジャンルがあります。
- 人気エリアの中古マンション
特に都市中心部や再開発地域は、供給が限られており、多少金利が上がっても需要が安定しています。 - コンパクトな中古戸建
新築より安く、維持費も抑えやすいため、金利上昇でローン負担を抑えたい層に人気です。 - 賃貸需要の高い投資用ワンルーム
自ら住むわけではないため、家賃収入とのバランスで購入判断する投資家が多く、金利上昇の影響は比較的限定的です。
これらの物件は、【希少性】か【コストメリット】のどちらか、あるいは両方を備えていることが多いです。
結局のところ、金利上昇下でも売れる家は「選ばれる理由」が明確です。
その理由を売主側が理解し、広告や内覧時にしっかり伝えることが、早期売却の決め手になります。
金利上昇時の不動産売却で失敗しないコツ✅
金利上昇局面での売却は、確かに条件が厳しくなります。
ですが、売り方次第でスムーズに進めることは可能です。ここでは3つのコツを紹介します。
売却タイミングは「金利が上がる前」が正解?
原則として、金利が上がる前に売却をスタートするほうが有利です。
理由はシンプルで、金利上昇がニュースになった時点で買い手は慎重になり、価格交渉が厳しくなるからです。
実際、私が関わったケースでも、2023年秋に売却開始した物件は、金利が上がる直前の3カ月で成約しました。一方、同じエリアで金利上昇後に売り出した物件は、同条件でも100万円の値下げが必要でした。
ただし「もう上がってしまったから遅い」というわけではありません。
金利が上がった後でも、価格や販売戦略を調整すれば十分売却は可能です。
複数社の査定を取り、価格戦略を柔軟に見直す
金利上昇時は、買い手の予算がタイトになるため、売り出し価格の見直しが重要です。
一度出した価格に固執してしまうと、売却期間が延び、結果的により大きな値下げを迫られるケースもあります。
- 査定は必ず2~3社以上から取る
- 価格の根拠(周辺成約事例・需要動向)を確認する
- 3カ月以上反響がない場合は価格調整を検討する
また、査定時に「この価格なら3カ月以内に売れる可能性」と「この価格なら半年かかる可能性」の両方を聞いておくと、市場の温度感がつかめます。
金利上昇時は「住宅ローン減税」などの制度活用も視野に
売主からすると見落としがちですが、買い手が利用できる制度を一緒に案内すると成約率が上がります。特に住宅ローン減税は、金利上昇局面で購入を後押しする材料になり得ます。
- 住宅ローン減税(控除期間や対象要件の確認)
- すまい給付金(年収条件を満たす場合)
- 自治体独自の補助制度(移住支援・子育て世帯向け)
例えば、買い手に「この物件だと年間◯万円の控除が受けられます」と具体的な数字を示すと、返済負担の不安が和らぎます。
制度情報は国土交通省や各自治体の公式サイトで最新情報を確認し、不動産会社とも共有しておくと安心です。
金利上昇期の売却は、「価格」「タイミング」「買い手の条件」という3つのバランス勝負です。
どれか一つだけ整えても成果は出にくいため、総合的に戦略を組むことが成功の近道になります。
それでも家が売れないときの対策✅
金利や価格戦略を見直しても、タイミングや条件によってはなかなか売れないことがあります。
そんなときは、発想を少し変えて「売る」以外の選択肢や、物件の魅力を底上げする方法を検討しましょう。
賃貸に切り替えるという選択肢
一時的に売却を止め、賃貸として貸し出す方法です。
家賃収入でローン返済をまかないながら、金利や市場環境が落ち着くのを待てます。
- 賃貸需要の高いエリアなら安定収入が見込める
- 将来的に再度売却する場合、ローン残債を減らせる
- 相続や住み替えの場合の資産運用にも有効
ただし、賃貸化すると売却タイミングの自由度が下がる点や、退去時の原状回復費用が発生する点には注意が必要です。
リフォームやインスペクションで価値を高める
外観や内装の印象は、購入希望者の判断に直結します。
金利上昇期は特に「買う理由」が求められるため、見た目や安心感の向上が効果的です。
- 水回りや壁紙の部分リフォームで印象を刷新
- ホームステージングで生活イメージを演出
- インスペクション(建物検査)で構造的な安心を証明
特にインスペクションは、売主が物件状態を開示しているという信頼感を生み、契約スピードを早めるケースもあります。
「囲い込み」に注意!適切な不動産会社選びがカギ
売れない原因が、実は不動産会社の販売戦略にある場合も少なくありません。
特に注意したいのが「囲い込み」。
これは、他社からの買い手紹介を断り、自社で買い手を見つけようとする行為です。結果として販売チャンスを逃し、売却期間が延びることがあります。
- レインズ(不動産情報共有システム)への登録状況を確認する
- 活動報告の内容や広告掲載状況をチェック
- 担当者が売主に正直に状況を伝えているかを見極める
信頼できる不動産会社は、売れない原因を率直に分析し、改善策を提案してくれます。「売る姿勢が本気かどうか」が見分けるポイントです。
金利上昇下での売却は確かにハードルが上がりますが、戦略を変えれば出口はあります。
「売却一択」に固執せず、賃貸化・価値向上・業者見直しといった複数のカードを持つことが、最終的な成功につながります。
不動産売却に関する不安・疑問はこちらで全解消!
▼▼▼
