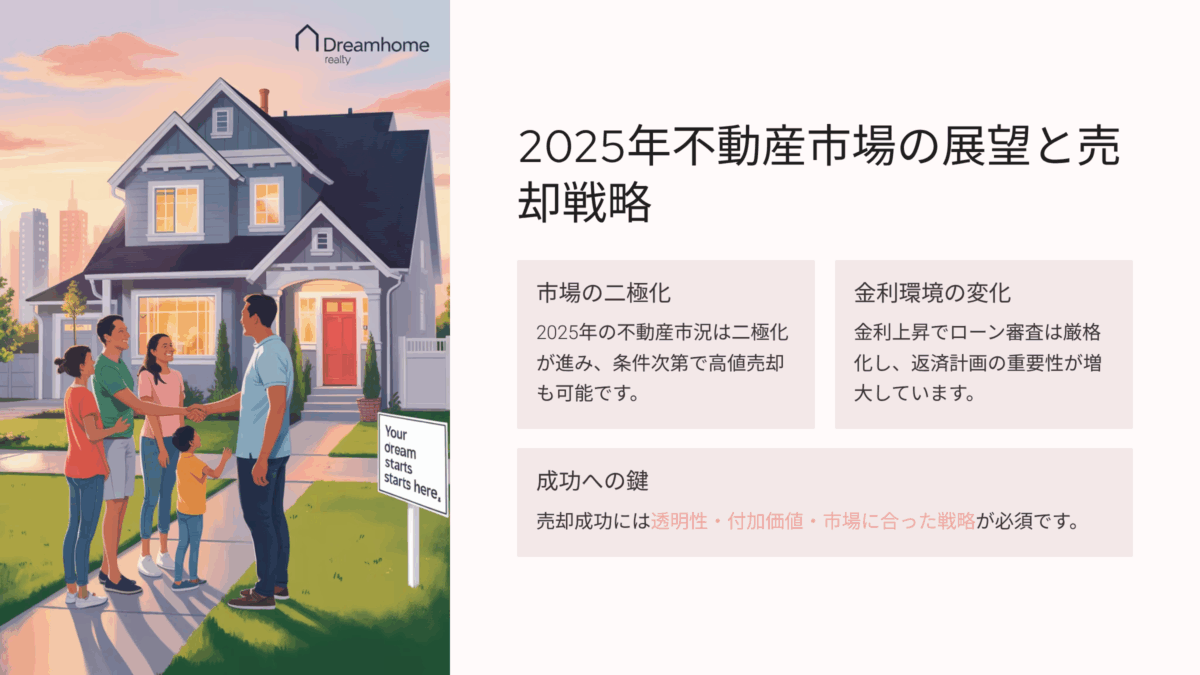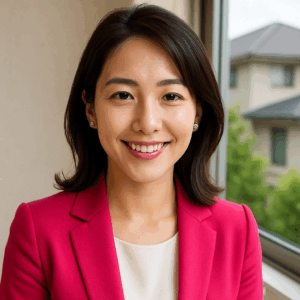
コロナ後の不動産市況は、価格動向から売買の進め方まで大きく変わりました。現場の実感と最新データを交えて解説します。目次を見て必要なところから読んでみてください。
コロナ後の不動産市況はどう変わった?【2025年時点の実感】
「コロナ禍を経て、不動産市況は結局どうなったの?」
そう疑問に思っている方、多いのではないでしょうか。
コロナ前は好調だった不動産市場も、2020年以降は売り手・買い手双方の動きが変わりました。
ただ「値上がりした」という一言では語れないのが今の実態です。
あなたも、
・「この先、物件価格は下がるの?」
・「売るなら今がベスト?」
・「地方と都心、どっちが有利?」
こんな疑問を持っていませんか?
ここでは、2025年現在の不動産市況を、数字と現場感覚の両方から整理します。
数字だけでは見えない「肌感覚」も含めてお伝えするので、今後の判断材料にしていただければと思います。
目次
- 不動産価格の動き:コロナ前後でどう変わった?
- 売却市場と購入市場の温度差
- 地方・郊外エリアの価格上昇とその理由
- 都心部のワンルーム・投資用物件の今
不動産価格の動き:コロナ前後でどう変わった?
まず、価格は上がったのか下がったのか?
結論から言うと、全国的には上昇基調です。ただし、上がり方に地域差があります。
国土交通省の地価公示によると、2024年時点で全国平均は前年比+1.6%。
コロナ直後の2020年は一時的に下落しましたが、金融緩和と住宅需要の変化により反発。
特に都市近郊の住宅地は2021年以降、コロナ前の水準を大きく上回っています。
現場での感覚としても、「価格が落ちる前に買いたい」という需要は根強く、売り出せば短期間で決まる物件もまだ多いです。
一方、築古や立地条件が悪い物件は、価格を下げても動きが鈍いまま。
つまり、二極化がより進んだ印象です。
売却市場と購入市場の温度差
ここ数年、不動産市況の特徴は「売り手と買い手の温度差」にあります。
売り手側は「まだ高く売れる」と考えがち。
しかし、買い手側は金利上昇や生活コストの増加でシビアに価格を見ています。
私が仲介に入ったある案件では、売主が「近所の相場より500万円高くても売れる」と強気でしたが、結果的に半年経っても申込みゼロ。
価格を相場並みに下げた途端、2週間で契約成立しました。
買い手は慎重でも、「納得価格」なら動く。
この温度差を理解して価格設定することが、2025年の不動産売却では必須です。
地方・郊外エリアの価格上昇とその理由
意外かもしれませんが、コロナ後に最も変化したのは地方と郊外です。
テレワーク定着や移住支援策で、都市圏から離れたエリアへの需要が増加。
特に新幹線や高速道路アクセスの良い地方都市では、2020年比で10〜15%の値上がりを記録しています。
例えば長野県のある市では、コロナ前は坪単価10万円台だった住宅地が、現在は15〜18万円に。
地元不動産会社によれば「首都圏からの移住希望者が価格を押し上げている」とのことです。
ただし、人口減少が進む地域では上昇の波は限定的。
需要増が一過性で終わる可能性もあるため、長期目線では慎重な判断が必要です。
都心部のワンルーム・投資用物件の今
コロナ直後に空室リスクが懸念された都心部のワンルームですが、2023年以降は回復傾向。
賃貸需要はインバウンド再開と単身世帯増加で戻りつつあります。
ただ、投資用物件の不動産市況には注意点があります。
金利上昇により利回りの見直しが進み、以前ほどの高値売却は難しくなっています。
特に築20年以上の区分マンションでは、表面利回りが5%台に留まるケースも珍しくありません。
投資家の間では、「短期売却益より長期保有でのインカムゲイン重視」にシフトする動きも見られます。
売却を考えるなら、賃貸稼働率や修繕履歴など、購入後の運用イメージを明確に提示することが重要です。
まとめ:2025年の不動産市況で動くなら「情報の鮮度」がカギ
2025年の不動産市況は、価格が高止まりする一方で、物件ごとの評価がシビアになっています。
高く売れる物件もあれば、条件次第では売れ残る物件もある。まさに選別の時代です。
もし今、売却や購入を検討しているなら、
・直近の成約事例を必ず確認する
・相場感を複数の不動産会社から得る
・買い手目線で物件価値を整理する
この3つを意識すると良いでしょう。
市場の変化は半年単位で進みます。
「いつか動こう」ではなく、「最新情報を得たらすぐ動ける状態」にしておくことが、後悔しない不動産取引の秘訣かなと思います。
リアルな現場で感じる「買主・売主」の変化
コロナ前後で、不動産市況そのものの数字はもちろんですが、現場で向き合う「人」の動き方が大きく変わりました。
数字のグラフでは見えない、リアルな空気感です。
売主の意識変化:早期売却か、価格維持か
以前は「とりあえず高く出して様子を見る」という売主が多かったのですが、2023年頃からは二極化が進んでいます。
ひとつは「価格よりスピード重視」派。
相続物件や空き家など維持コストが重く、1〜2カ月以内の成約を目指して価格を相場より低めに設定します。
実際、こうした案件は広告開始から1〜3週間で決まることが多いです。
もう一方は「時間をかけても高値維持」派。
ローン残債が少なく、生活に余裕がある人ほど、売却を長期戦で考えます。
ただ、このタイプは価格調整のタイミングを逃すと半年以上売れ残るケースもあり、相場観のアップデートが重要になっています。
買主の傾向:実需重視か、投資重視か
買主側も二つの流れがはっきりしています。
実需派は「住宅ローン金利が上がる前に買いたい」という動機が強く、物件の条件よりも総返済額を重視します。
この層は内覧後の意思決定も早く、「この条件なら即決します」というケースが目立ちます。
一方、投資派は利回りや修繕履歴に非常に敏感。
コロナ禍を経て運用リスクを痛感しているため、「入居率が高くても、今後の賃料下落が読めない物件」には手を出しません。
数字で裏付けられない案件は、ほぼスルーされます。
内覧・商談の変化:非対面・オンライン化の定着
コロナ期に一気に広がったのが、オンライン内覧や非対面契約。
2025年の現場でも、これが完全に定着しています。
特に地方物件や投資用物件では、買主が現地を訪れず、動画や360度カメラ映像だけで契約まで進むことも珍しくありません。
私も最近、北海道の物件を東京の投資家がオンライン内覧のみで購入したケースを経験しました。
もちろん、非対面の便利さと同時に「現地でしか分からない欠点」を見落とすリスクもあります。
そのため、信頼できる現地の不動産会社やインスペクション(建物検査)の活用が以前にも増して重要になっています。
若年層・高齢者の動き方の違い
年齢層によって、不動産市況の見え方や動き方も大きく違います。
20〜30代の若年層は、住宅ローンの借入可能額を最大限に活かして「今の生活にフィットする家」を優先。
ITリテラシーが高く、物件探しから契約までほぼオンラインで完結させる傾向があります。
一方、60代以上の高齢者は、現物を見て納得するまで契約しない方が多いです。
また「終の住処」を意識して、バリアフリーや医療機関へのアクセスなど、生活の質を重視します。
この世代は、売却側に回る場合も多く、「子どもに残すより、現金化して老後資金に」という動きが目立ちます。
金利とローン審査の動向【2025年版】
「金利が上がったら住宅ローンはどうなるの?」
「ローン審査が厳しくなったって聞くけど本当?」
この2つは、ここ1年でよく相談されるテーマです。
金利の動きは、不動産市況に直結します。
2025年の今、住宅ローンを利用して不動産を購入・投資する人にとって、知っておくべきポイントを整理します。
住宅ローンの最新金利水準と審査状況
2025年8月現在、都市銀行の変動金利は0.45〜0.6%台(優遇後)、10年固定は1.1〜1.3%台が一般的です。
2023年頃までは0.3%台の変動金利も珍しくありませんでしたが、日本銀行の政策金利引き上げと市場金利上昇により、じわりと上がっています。
現場の感覚では、金利上昇を理由に「予算を500万円ほど下げる」買主が増えました。
金利が0.3%上がるだけで、35年ローンなら総返済額は数百万円単位で変わりますから、慎重になるのは当然です。
ローン審査が厳しくなったって本当?
「厳しくなった」というのは半分正解です。
住宅ローンの基本的な審査項目(年収、勤続年数、他ローン残高、信用情報)は変わっていません。
ただ、金利上昇や物価高の影響で、金融機関が「返済負担率」をより厳密に見るようになりました。
例えば以前は年収500万円で年間返済額が175万円程度まで許容されたケースでも、今は150万円前後が目安になることがあります。
これは「将来的な金利上昇にも耐えられるか」を見るためです。
投資用ローンではさらに慎重で、家賃収入の見込みに対して「空室リスク」を差し引いたシミュレーションを提出させる銀行も増えました。
このあたりは、不動産投資の経験者からも「昔より数字の根拠を求められる」という声が多いですね。
フラット35や変動金利の選び方の傾向
金利上昇局面では「固定金利が安心」と言われますが、2025年の選び方はもう少し複雑です。
フラット35は、金利が1.8〜2.0%台と高めですが、全期間固定で返済計画が立てやすいことから、共働き世帯や長期的に安定した返済を望む層に人気です。
一方で、初期返済額を抑えたい層は、依然として変動金利を選択します。優遇後の金利が0.5%前後なら、総返済額はまだ固定より低く済むからです。
最近の傾向としては、
- 最初の10年は変動で低金利を享受し、その後の繰り上げ返済や固定への切り替えを視野に入れる「ハイブリッド戦略」
- 頭金を多めに入れて借入額を抑え、金利上昇リスクを回避する方法
この2つが増えています。
不動産業界の裏側:現場で起きている新しい常識
ニュースや統計では見えない変化が、不動産市況の現場では日々起きています。
「え、今はそんなやり方が当たり前なの?」と感じるようなことも増えました。
ここでは、仲介の立場から見える“新しい常識”をお伝えします。
仲介業者が感じている市況の変化とは
一番の変化は「物件が動くスピードの二極化」です。
条件が整った物件は1週間以内に申込みが入る一方、条件が不足している物件は半年以上売れ残ることも。
コロナ前は「とりあえず広告に出して様子を見る」案件もそこそこ動きましたが、今は情報量が多く、買主が即座に比較できるため、“平均的な物件”は埋もれやすくなっています。
仲介としては、販売戦略を立てる時点で「短期決戦型」か「長期育成型」かを見極める必要が出てきました。
物件が売れやすい「条件」とは?
2025年時点で売れやすい条件は、立地や価格だけではありません。
現場で特に効果を感じるのは以下の3つです。
- 修繕・リフォーム履歴が明確
外壁塗装や水回り更新の時期が分かるだけで、買主の安心感が違います。 - 適正価格+少しの魅力付け
相場より安いだけではなく、家具付きやホームステージングなどで印象を上げる工夫。 - 情報開示の透明性
瑕疵(かし)の有無や周辺環境の懸念点を隠さず伝えることで、内覧後のキャンセルを防げます。
価格交渉に入る前から「信頼できる物件」と思ってもらえるかが勝負です。
コロナ後に増えたトラブルとその対処法
コロナ後、私が実感するのは「契約後トラブル」の増加です。
- オンライン内覧だけで契約したが、引き渡し後に「想像と違う」とクレーム
- 引っ越し日や鍵の受け渡し日を巡る日程トラブル
- 建物の細かな傷や設備不具合を巡る修繕費用の争い
これらの多くは、事前の説明不足が原因です。
私の現場では、写真や動画だけでなく、インスペクション報告書を事前に共有することでトラブル率が半減しました。
「契約前に分かっていた」という事実は、後のクレーム抑止力になります。
媒介契約やインスペクションの注目度アップ
以前は媒介契約(一般・専任・専属専任)の違いをよく理解していない売主も多かったのですが、最近はネット情報の影響で、契約内容を比較して選ぶ方が増えています。
特に専任媒介のメリット(販売活動の一元化・進捗報告義務など)を理解して指名するケースが目立ちます。
また、インスペクション(建物検査)は、2020年代前半までは「新築じゃないなら一応やるか」程度の認識でしたが、今は“売れるための必須条件”になりつつあります。
検査済みというだけで、内覧予約数が1.5倍になる事例もありました。
2025年以降に不動産を売却する人へのアドバイス
「2025年から先、不動産価格は下がるのか、それとも維持されるのか?」
売却を検討している人にとって、この答えはとても気になりますよね。
でも、正直に言うと“絶対の正解”はありません。
ただ、今の不動産市況を踏まえれば、動き方のヒントは確実にあります。
ここでは2025年以降に売却を考える方へ、現場での経験からアドバイスをお伝えします。
今後の市況予測と売却戦略
多くのアナリストは、2025〜2027年にかけて「緩やかな価格調整」があると見ています。
理由は、金利の上昇傾向と新築供給の増加、そして人口減少です。
私の実感としても、「高値更新ペースは落ち着きつつある」状態です。
とはいえ、立地や条件次第では依然として高値成約も可能。
つまり、全体が下がるのではなく、物件ごとの差がさらに拡大します。
戦略としては、
- 価格が高止まりしている間に売る「先行逃げ切り型」
- 価値を高めるリフォームや情報開示で選ばれる物件にする「付加価値型」
この2つが有効です。
査定価格に振り回されないために
売却相談の現場でよくあるのが、「一番高い査定額を出した会社に決める」ケース。
気持ちは分かりますが、これが失敗の原因になることも多いです。
不動産会社によって査定額が数百万円違うことは珍しくありません。
高く提示したのは単なる“媒介契約を取るための数字”ということもあります。
実際に私が関わった案件で、最初は高額査定を信じて半年売れず、結局300万円値下げして売れたケースがありました。
相場感をつかむためには、最低3社の査定を比較し、その根拠を必ず確認することが大事です。
売却するなら「どんな物件が有利」?
2025年以降に有利なのは、
- 駅徒歩10分以内の利便性が高い物件
- 管理状態や修繕履歴がしっかりしているマンション
- 庭付きや駐車場付きなど生活の快適性が高い戸建て
反対に、築古で設備更新がされていない物件は価格競争に巻き込まれやすいです。
その場合、外壁塗装や水回り交換など、見た目と使い勝手を改善する投資が成約スピードを大きく変えます。
成功事例に学ぶ!コロナ後の上手な売却法
ある売主は、地方都市の築20年戸建てを売却するにあたり、インスペクション+軽リフォーム+ホームステージングを実施。
総額80万円の投資でしたが、結果的に相場より120万円高く売れました。
別のケースでは、都心ワンルームを売却する際に、賃貸契約の更新時期を考慮して空室状態で販売。
内覧の自由度が上がり、想定より2カ月早く成約しました。
どちらにも共通しているのは、「買主が安心・納得できる状態」を作ってから売り出したという点です。
価格交渉の場面でも、情報や状態の透明性が強い武器になります。
不動産売却に関する不安・疑問はこちらで全解消!
▼▼▼