売却後の手続きとお金の流れ
ローン完済・抵当権抹消の流れ
不動産の売却が成立し、売買契約が締結されたあとも、やるべき手続きはまだ続きます。中でも重要なのが「住宅ローンの完済」と「抵当権の抹消」です。
売却代金を受け取ったら、まず最初にローン残債を一括返済します。そして金融機関から「抵当権解除書類(弁済証書など)」を受け取り、法務局で抵当権を抹消する登記手続きを行う流れとなります。
下記は基本的な流れの概要です。
| 手続きのステップ | 内容と注意点 |
|---|---|
| 1. 売買代金の決済 | 買主からの入金でローン完済に充てる |
| 2. ローン完済 | 金融機関へ残債一括返済(通常は司法書士が立ち会い) |
| 3. 抵当権抹消登記の申請 | 売主が行う。司法書士に依頼するのが一般的 |
| 4. 抹消完了(売却成立) | 名義も抵当も外れ、買主へ正式引き渡し |
抵当権が残ったままでは、買主が安心して購入できません。そのため、引渡しまでにこれらの手続きをセットで済ませることが前提となります。
司法書士報酬は数万円ほどですが、売却諸費用の中に含めて見積もっておくと安心です。
共有名義だった場合の入金・清算はどうなる?
離婚を伴う不動産売却では、夫婦で共有名義になっているケースがよくあります。この場合、売却代金は名義割合に応じて分配されるのが基本です。
| 例:売却価格4,000万円、名義割合=夫50%:妻50%の場合 |
|---|
| 売却代金はそれぞれ2,000万円ずつが取り分となる |
| ローンも共有であれば、返済分も名義割合に応じて清算 |
ただし、以下の点に注意が必要です:
- 実際のローン返済負担に偏りがある場合は、別途取り決めて精算する
- 財産分与の対象となるため、名義と違う分け方も可能(合意次第)
清算内容は合意書を作成しておくと後々のトラブルを防げます。不安な場合は、弁護士や司法書士に同席してもらうのも有効です。
売却益にかかる税金と確定申告
譲渡所得が出たらどうなる?
家を売って利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。以下のような計算式で、課税額が算出されます。
| 計算式(基本形) |
|---|
| 譲渡所得 = 売却額 −(取得費+譲渡費用) |
この譲渡所得に対して、保有期間に応じて税率が変わります。
| 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年以下の短期 | 約39.63% |
| 5年超の長期 | 約20.315% |
高額な税負担に見えるかもしれませんが、実際にはさまざまな控除制度が適用可能です。
離婚時の特例控除や非課税制度
離婚にともなう住宅売却では、通常の売却とは異なる税制上の特例を活用できる可能性があります。
主な控除・制度は以下の通りです。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 居住用財産の3,000万円特別控除 | 売却益から3,000万円まで非課税になる制度(※一定要件あり) |
| 譲渡損失の繰越控除 | 売却損が出た場合、給与所得などと相殺できる制度 |
| 財産分与による非課税 | 離婚時の財産分与で譲渡された財産は課税対象外になる場合も |
3,000万円控除を受けるには、確定申告が必要です。また、離婚協議書に「財産分与のための売却」と明記されていれば、控除や非課税の適用がスムーズになります。
不安な場合は、税理士と連携しながら進めると、申告ミスや損を防ぐことができます。
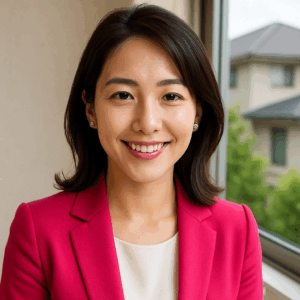
家を売ったら終わり――と思われがちですが、売却後こそ「本当の整理」が始まります。特に離婚が絡む場合、感情の整理だけでなく、お金と手続きの整理も重要なパートになります。
印象的だったご相談のひとつに、「売った後に税金が来るなんて知らなかった…」というケースがありました。譲渡所得が出ると、タイミングによっては翌年の2月〜3月に確定申告が必要になり、大きな納税額になることもあります。
しかしその方は、売却の初期段階で適切なアドバイスを受けていれば、本来は3,000万円控除が適用されて、税金ゼロにできた可能性があったのです。知らなかっただけで、本来守れたはずのお金を失ってしまったという悔しい結果でした。
その経験から、私は常に「売却を考えた時点で、出口までの設計を一緒に描きましょう」とお伝えしています。
家を売ったあとのお金、手続き、確定申告――。どれも難しく感じるかもしれませんが、一つひとつ順を追って対応すれば、必ず整います。未来を前向きに歩むための土台づくり。それが、売却後の“やるべきこと”なのです。
税金のことも、清算のことも、気軽に聞ける相手がいると心が軽くなります
ひとつずつ丁寧に、確実に前へ。一緒に整理していけるパートナーが、あなたの支えになります
✅ 三井のリハウスに相談してみる
👉 売却後の手続きを経て、“気持ちに整理がついた”体験談はこちら
離婚と住宅ローン、売却が解決の糸口になった 実際にいくらで売れたのか、体験をもとにご紹介します。
